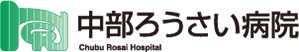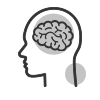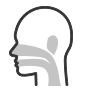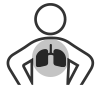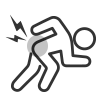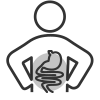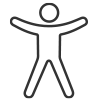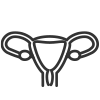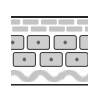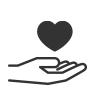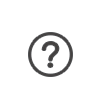症状/疾患・部位 からさがす
- TOP
- 症状/疾患・部位 からさがす
- 「た行」の症状/疾患
「た行」の症状/疾患
- 体重減少
-
食事量は変わらないのに体重が減る場合は糖尿病や甲状腺機能亢進症(バセドウ病)など内科疾患の可能性があります。下痢や粘血便は大腸炎、胃の痛みや吐き気・食思不振などがあれば胃炎や胃・十二指腸潰瘍を疑います。血液疾患である悪性リンパ腫は消化器に病変を生じることがあり、体重減少で病気がみつかることもあります。拒食症などの摂食障害では極端に体重減少があるのにも関わらず、本人の自覚に乏しいのが特徴です。
- たちくらみ
-
急に立ち上がったときに感じるふらっとしためまいをたちくらみといいます。通常はわずかな時間で治ります。立ちくらみの多くは臥位や座位から立ち上がった時に起こる脳貧血(起立性低血圧)が原因です。体位の変化に血圧調整がついていかないため立ち上がった時に血圧が急に下がります。加齢、糖尿病やパーキンソン病などの自律神経障害を伴う疾患で認められます。小児や若年者でも立っていると気分が悪くなる、たちくらみがするなどの「調節性障害」を起こすことがあり、自律神経のはたらきがうまくいかない症状です。血圧調節に関わる自律神経失調や心因性などいろいろな原因があります。
- たん
-
たんは気道内の分泌物です。細菌やウイルスなどの異物の侵入を防ぐ働きがあります。通常のたんは白く透明ですが、細菌感染をおこすとたんの色が黄色・緑色になります。脳萎縮や多発脳梗塞が起こると飲み込む反応(嚥下反射)や嚥下の力が弱くなるためたんが出しづらくなります。誤嚥性肺炎の原因になるためたんをしっかり出せるようにする必要があります。たんに血が混じっている場合は肺がんや肺結核などの否定が必要です。脳梗塞や心筋梗塞予防に抗凝固・抗血小板薬を飲んでいると出血しやすくたんに血が混じることもあります。
- 多汗症
-
過剰に汗をかく病気を多汗症といいます。全身の汗が増加する全身性多汗症と手のひらや足の裏、脇、顔など体の一部に汗が増える局所性多汗症があります。卵巣機能の低下した更年期にはホットフラッシュとともに顔面・頭部の異常発汗を認めることがありますが生理的な現象で疾患ではありません。
- 多発性硬化症
-
大脳・小脳・脊髄・視神経など多数の部位に自己免疫異常による炎症がおこり、手足の運動麻痺やしびれ感、ふらつき、排尿障害など多様な症状を呈します。若い女性に発症することが多く、回復と再発を繰り返して運動・感覚障害や知的機能の低下が進行していく場合があります。急性期はステロイドホルモン剤や免疫グロブリンを使用して炎症を抑えます。その後は再発予防薬を用い、新しい病変の出現や大脳皮質の萎縮を予防します。(厚労省指定難病)
- 多発嚢胞腎
-
ADPKD(常染色体優性多発性嚢胞腎)は、腎臓にたくさんの嚢胞(水分でできた袋)ができる遺伝性の病気です。嚢胞は年齢とともに増え、徐々に腎機能が低下します。60歳までに約半数の患者さんが末期腎不全(透析か移植が必要になること)になりますが、腎機能低下のスピードは個人差が大きく、同じ家系の中でも進み具合にはかなりの幅があります。脳動脈瘤や肝臓の嚢胞、心臓弁膜症などの病気を合併することもあり、みつかればそれぞれに治療をします。腎臓に対しては降圧治療や積極的な飲水、治療の条件を満たせばトルバプタンという嚢胞増大をおさえる薬などで治療します。
- 胆石症
-
胆道にできた結石の総称です。結石の存在部位により、胆嚢結石、総胆管結石と呼ばれます。上腹部痛、背部痛、肝機能障害、発熱、黄疸などを生じます。検査は血液検査、腹部超音波検査、CT検査、MRI検査、内視鏡検査、超音波内視鏡検査等を行います。治療は薬物治療、内視鏡治療、手術などが行われます。胆石手術の多くは開腹ではなく腹腔鏡手術が行われています。
- 胆道がん
-
胆道がんは、胆道にできる悪性腫瘍です。周囲のリンパ節、肝臓、肺などの臓器に転移したり、膵臓などの周囲の臓器に浸潤(がんが周囲に染み出るように広がっていくこと)したりすることがあります。黄疸、右上腹部痛、体重減少などの症状があります。血液検査、腹部超音波検査、CT検査、MRI検査、PET検査、内視鏡検査などで検査します。治療は手術、薬物治療です。
- 大腿骨近位部骨折
-
高齢者が転倒し、股関節痛で歩けなくなる場合は、ほとんどが本骨折です。1週間寝たきりでいると10-15%の筋力低下を生じ、著しく日常生活機能を低下させます。速やかに手術を行い、早期リハビリテーションにより機能を保つことが大事です。中部ろうさい病院整形外科ではなるべく受傷後48時間以内に骨接合術を行うようにしています。また骨粗鬆症により骨折しやすい状態にあるため、次の骨折を予防するために骨粗鬆症の治療も入院中に開始します。
- 大腸がん
-
大腸がんは、大腸(結腸・直腸)に発生するがんで、悪性腫瘍です。腺腫という良性のポリープががん化して発生するものと、正常な粘膜から癌発生するものがあります。早期の段階では自覚症状はほとんどなく、進行すると、血便(便に血が混じる)、下血(腸からの出血)、下痢と便秘の繰り返し、便が細い、便が残る感じ、おなかが張る、腹痛、貧血、体重減少などの症状があります。注腸造影検査、下部消化管内視鏡検査、腹部超音波検査、CT検査、MRI検査、PET検査などを行います。治療には、内視鏡治療、手術、薬物療法、放射線治療などがあります。
- 大腸ポリープ
-
大腸の表面の、粘膜の一部がイボのように隆起してできたもののことを大腸ポリープといいます。当院では、大腸カメラで切除対象のポリープが見つかった場合、そのまま日帰りが可能な大腸ポリープ切除術を行っています。通常のポリープ切除術は、スネアという特殊なワイヤーでポリープの根元を絞めて高周波電流を流して切除しますが、近年、高周波電流を流さず、スネアでポリープの根元を絞めて切除するコールドスネアポリペクトミーが主流になってきており、中部ろうさい病院でも施行件数が増えてきています。
- 大動脈解離
-
大動脈とは心臓から全身へ血液を送る太い血管です。この血管は外・中・内の三層構造ですが、一番内側の内膜が縦に裂けてしまう病気が大動脈解離です。動脈硬化・高血圧・喫煙・糖尿病・脂質異常などが発症リスクです。初発症状は胸痛・背部痛です。脳梗塞を同時に起こす場合があります。上行大動脈解離で特に死亡率が高く、緊急の対応が必要です。
- 男性性機能障害(ED)
-
男性性機能障害は勃起障害(ED)と射精障害の2疾患が大半を占めています。勃起障害は勃起を発現できないか持続できないため満足な性交渉ができない状態を意味します。原因の半分は精神的な問題で残る半分が糖尿病、動脈硬化など生活習慣病です。射精障害は射精が全くできない、射精までに時間がかる(遅漏)など多様な疾患群を含んでいます。勃起障害、射精障害ともに子供ができない(男性不妊症)原因となるため的確な診断とエビデンスに裏付けられた効果的な治療法で対処するこが大切です。
対応する診療科
- 聴覚スクリーニング(新生児)
-
新生児の1000人に1〜2人に難聴があると言われています。新生児聴覚スクリーニングは赤ちゃんが受けることのできる聞こえの簡易検査で、痛みはなく安全で赤ちゃんが寝ている間に、11 分ほどで終了します。専門の施設でさらに詳しい検査を受けた方がよいかどうかを選別するための検査です。
- ちくのう症(副鼻腔炎)
-
ちくのう症(副鼻腔炎)とは、副鼻腔の粘膜が何らかの原因で炎症を起こしている状態のことです。感染、アレルギー、カビ(真菌)、腫瘍、歯など様々な原因で臭い鼻水、鼻づまり、顔面痛、嗅覚障害などの症状が出現します。内視鏡下鼻副鼻腔手術(ESS)を行っています。現在主流で行われている手術で体への負担の少ない手術です。また安全に手術を行うためにナビゲーションを使用しています。
対応する診療科
- 智歯周囲炎(おやしらず)
-
智歯(親知らず)の萌出に際してみられる周囲炎症を特に智歯周囲炎(ちししゅういえん)と呼び、20歳前後の若い人に発生する頻度の高い疾患です。最も遅く、また最も後方に萌出する智歯は、萌出異常をきたし、完全萌出せず歯肉が歯冠を部分的に覆ったままになりやすいため、不潔で、歯肉の炎症をおこしやすくなっています。 智歯周囲炎が周囲の軟組織や顎骨(がっこつ:あごの骨)に波及して顔が腫れたり、口が開きにくくなったりすることがあります。 抗菌薬や消炎鎮痛薬を投与し消炎させた後、萌出位置の異常があったり、炎症をくり返しているような場合は、智歯を抜歯します。
対応する診療科
- 中枢神経麻痺後痙縮
-
脳卒中や脊髄損傷患者の後遺症として痙縮(けいしゅく)が高頻度に出現します。初期には運動療法や内服治療により症状が改善しますが、程度が増大し日常生活動作が障害されるようになります。そのような場合は、その原因となる筋にボツリヌストキシンを注射して、過剰な筋肉の収縮を軽減させます。中部ろうさい病院リハビリテーション科では低周波装置や超音波診断装置などを使用して安全性を確保しながら処置を実施しています。
対応する診療科
- 中大脳動脈閉塞症・狭窄症
-
中大脳動脈閉塞症・狭窄症を示す慢性期脳梗塞に対して側頭部の頭皮を栄養する血管と中大脳動脈を吻合するバイパス手術を行い脳血流の確保を図ります。
対応する診療科
- 痛覚変調性頭痛
-
片頭痛・緊張性頭痛の患者さんが慢性的に「痛い」状態にあると実際は痛みが生じる筋緊張や血管拡張はないのに痛くなってしまう・・・脳が痛みを覚えてしまっている状態といわれます。痛みを感じやすくなっている状態といってもよいでしょう。片頭痛や緊張性頭痛の治療と同時に痛みの閾値を正常化するために抗うつ剤やセロトニン再吸収阻害剤の内服薬が有効です。
- 痛風・高尿酸血症
-
血清尿酸値7.0 mg/dL以上は高尿酸血症となります。尿酸値が高いだけでは自覚症状はありませんが、長期間の高尿酸血症により関節・足先などに結晶となった尿酸がたまり炎症が生じ、激痛の痛風発作が起こります。 また腎臓結石や尿管結石の原因となり、背部などに激痛を生じます。尿酸の生成抑制薬や尿への排泄促進薬で治療を行います。食事療法としてプリン体の摂取制限が必要となります。
- 手足のしびれ
-
日本語では「しびれ」は動きが悪い時にも使うことばですが、医療の場面での「しびれ」は感覚(感じかた)の異常を意味します。しびれには何もしなくても痺れを感じる自発痛や、触られたり物に触れるといつもと違う感じがするしびれ、いつもより鋭く感じる、鈍く感じるなど色々の場合があります。皮膚の感覚は皮膚から末梢神経、脊髄を経由して大脳感覚中枢に刺激を伝える伝導路を通過します。この経路のどこかに異常があるとしびれ・痛みといった感覚障害が認められます。神経系の異常ばかりでなく椎間板ヘルニアなど整形疾患が原因となることが一般的です。
- 手足のひえ・冷え性
-
低血圧・貧血・膠原病・甲状腺機能低下症・閉塞性動脈硬化症・バージャー病などの血行障害で認められます。筋肉量の低下(サルコペニア)を起こした高齢者や痩せた女性に多いといわれます。運動不足でも冷えが起こりやすいといわれています。そのほか自律神経機能の乱れで体温調節がうまくできず冷えを感じることもあります。適宜な運動、ストレスへの配慮などが必要です。
- 低身長
-
小児内分泌専門医が、低身長や思春期早発症、甲状腺疾患などの疾患について、個々の患者様の日常生活の質を高めることができるように、ご家族と協力して治療を進めて行きます。身長が低い・身長の伸びが悪い、思春期が早いあるいは思春期が遅いなどは病気ではなく体質の場合も多いですが治療が必要な疾患もありますので小児科外来にご相談ください。
- 低髄液圧症候群
-
交通事故・スポーツ外傷などが原因で脳脊髄を覆う膜(硬膜)が破れ、脳脊髄が髄液腔外へ漏れて減少するため頭痛・頚部痛・めまい・耳鳴り・倦怠感・不眠・もの忘れなどさまざまな症状が起こります。仰臥位など寝ている姿勢ではなんともないのに立ち上がると(立位)症状が出現することが特徴です。心因性の不定愁訴と区別がつきにくく、MRIやシンチグラフィーなどで髄液の漏れを証明しなければなりません。髄液が漏れている場所が確認できれば硬膜下血液パッチ(ブラッドパッチ)などの手術治療が可能です。
- 転移性肺腫瘍
-
転移性肺腫瘍とは、他の臓器でできたがんが血管やリンパ管をめぐって肺に到達し、できもの(腫瘍)になったものをいいます。もともと肺にある細胞ががんとなる、いわゆる(原発性)肺がんとは異なります。肺がんであれば、肺がんを専門とする医師が治療方針を決定しますが、転移性肺腫瘍の場合、その腫瘍の顔つきがおおもとのがん(原発巣)と同じであるため、原発巣を担当する医師が治療方針を決定し、もし手術が必要であれば呼吸器外科で手術を行います。
- てんかん(小児)
-
てんかんというと全身がガクガクとけいれんする病気だと思われるかもしれませんが、実際にはボーッとするてんかん発作や口が動くてんかん発作など症状は様々です。小児科ではMRIや脳波などの検査に加え、薬による治療を行っており定期的に通院されている方も多くいらっしゃいます。また、より精密な検査や外科手術などの専門治療が必要な場合には専門施設への紹介も行います。16歳以上になっても治療の継続が必要な場合は脳神経内科あるいは専門施設への紹介となる場合があります。
- 頭頸部がん
-
咽頭、喉頭、口腔、舌、耳下腺など様々な部位から発生する悪性腫瘍です。これらは主に耳鼻咽喉科で治療を行います。治療としては手術、放射線、薬物療法、免疫療法などが挙げられます。どの治療法が良いのかは症例によって異なるため、最適な方法を患者さんと相談して選択していきます。
- 頭頸部良性腫瘍
-
耳下腺、顎下腺、副鼻腔、甲状腺などの耳鼻咽喉科領域全般に発生する良性の腫瘍です。症状が現れないものから悪性腫瘍に準じた治療を必要とするものなど多岐に渡る種類があります。その種類に応じて、個々の患者様に適した治療方針を選択し、必要がある場合はに耳鼻咽喉科で手術を行っています。甲状腺良性腫瘍に対しては積極的に内視鏡下手術を選択しています。
- 統合失調症
-
幻覚・妄想を主体とした疾患で、人口100人に1人の発症率があります。適切な薬物療法により寛解を得ることを目標とした治療が行われます。
対応する診療科
- 糖尿病(1型糖尿病)
-
膵臓のランゲルハンス島にあるβ細胞の自己免疫機序による破壊により、絶対的なインスリン欠乏になる糖尿病です。発症のタイプにより、急性発症、劇症、緩徐進行に分類されます。比較的若年での発症が多く、日本人糖尿病患者の数%と言われています。急性発症、劇症タイプはすぐにインスリン自己注射療法の適応となりますが、緩徐進行型は進行がゆっくりですぐのインスリン治療を要しない場合があります。
対応する診療科
- 糖尿病(2型糖尿病)
-
日本人糖尿病患者の95%以上とも言われている比較的成人に発症するタイプの糖尿病です。ただ最近は肥満傾向の10代の若年発症も増えています。必ずしも肥満を伴うわけではありませんが、遺伝的体質に過食、運動不足、高齢などの生活習慣の乱れが加わることで発症します。インスリン分泌不全や抵抗性により相対的に必要なインスリン作用が得られず高血糖となります。食事と運動療法から内服薬やインスリン注射にて治療します。
対応する診療科
- 糖尿病性壊疽・難治性潰瘍
-
糖尿病性壊疽は糖尿病による下肢の血流障害を併発していることも多いため、形成外科が循環器内科と協力しながら血流評価と血行再建を行った上での手術治療や外用療法を行っています。静脈うっ滞性潰瘍などの難治性潰瘍は圧迫療法や陰圧閉鎖療法などを行いながら治療しています。
- 糖尿病性神経障害
-
糖尿病性神経障害は網膜症・腎症とならぶ糖尿病三大合併症のひとつです。血糖コントロールが不良な状態が継続すると末梢神経の神経軸索が細くなり感覚障害が起こります。糖尿病の神経障害は通常、足の指や足の裏の感覚障害から始まります。じんじんとしたしびれ感や足の裏に餅が張り付いたような異常感覚、時にヒリヒリした痛みを認めます。また神経障害のひとつである自律神経障害の症状として頑固な便秘や下痢、起立性低血圧(たちくらみ)が認められます。慢性症状のほかに急速な血糖コントロールや低血糖の頻発によって痛みの強い神経障害を起こしやすいことも知られています。
- 糖尿病性網膜症
-
糖尿病には腎臓障害や神経障害など様々な合併症が知られていますが、目の奥に出血を起こすなどの糖尿病網膜症が起きることがあります。中等度以上の網膜症にはレーザー治療を行うことがありますし、硝子体出血などの重度の網膜症には硝子体手術の適応となることがあります。網膜の中心部分で視力に重要な黄斑と呼ばれる場所に水がたまる黄斑浮腫に対しては硝子体注射が有効なことが多いです。
- 糖尿病・肥満(小児)
-
インスリン治療が必要な1型糖尿病や、食事・運動療法が主体となる2型糖尿病などを診療しています。また、最近増加傾向にある小児肥満に対して栄養指導など 生活習慣の改善の指導を行います。
対応する診療科
- 頭部外傷
-
転倒・転落や交通事故等で頭部を受傷された場合、脳神経外科で対応します。受傷後急性期(1週間以内)は症状の変化が大きく入院が必要な場合もあります。また、受傷して1カ月以上経過して発症する疾患(慢性硬膜下血腫)があります。歩きにくさや認知機能の悪化、頭痛が徐々に進行することが多く、まれには意識障害が出現します。外傷後に「おかしい」と感じたらの脳神経外科を受診して下さい
- 特発性大腿骨頭壊死症
-
主にアルコール多飲やステロイド薬による影響で大腿骨頭に骨壊死が起きて股関節が破壊される病気です。骨壊死した範囲が小さい場合は痛み止めなどの保存治療でも症状改善する可能性がありますが、骨壊死した範囲が大きい場合は骨壊死した部分は再生しないため、骨壊死した部分が圧壊して骨切り術や人工股関節置換術が必要になることが多いです。
- 突発性難聴
-
突然原因不明の難聴が発症し、耳鳴や耳が詰まる感じや、めまいが伴う場合があります。ステロイドの治療を行います。ステロイド治療に反応が悪い場合は、鼓室内ステロイド投与をお行います。
- どこを受診すれば良いかわからない
-
身体症状があっても何科に受診すれば良いかわからない、健康不安などはまず総合内科を受診しましょう。中部ろうさい病院では婦人科疾患以外の女性特有の疾患、女性医師への相談を希望するときは女性のための総合内科である女性診療科で受けています。