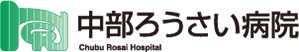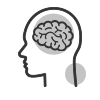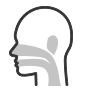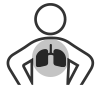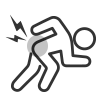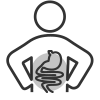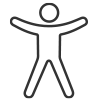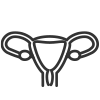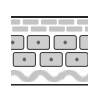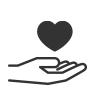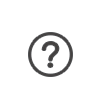症状/疾患・部位 からさがす
- TOP
- 症状/疾患・部位 からさがす
- 「さ行」の症状/疾患
「さ行」の症状/疾患
- サルコペニア
-
サルコペニアとは、加齢による筋肉量の減少および筋力低下のことです。いわゆる「足腰の弱り」という状態に近いかもしれません。サルコペニアになると歩く、立ち上がるなどの日常生活動作が不自由になり転倒しやすくなってしまいます。定期的な運動と適切な栄養を摂ることを心掛けサルコペニアを予防することが高齢者の健康につながります。「手足が細くなった」「重いものが持てない」「歩くのが遅くなった」などの症状があればまずかかりつけ医に相談しましょう。
- 三叉神経痛
-
三叉神経痛とは顔の感覚を脳に伝える脳神経(三叉神経)の異常興奮が原因で顔に激痛が起こる疾患です。片側のみに症状があり、洗顔・髭剃り・食事(ものを噛む)などの知覚刺激や動作がトリガー(ひきがね)になります。通常の鎮痛薬は効果が乏しく、疼痛コントロールには抗てんかん薬が著効します。典型的三叉神経痛は脳血管が神経を圧迫することによって起こるため内科的治療に抵抗性の場合は血管の圧迫を解除する手術を行うこともあります。糖尿病や多発性硬化症などの疾患に伴うことも知られています。
- 失神
-
失神とは突然おこる短い時間の意識消失です。気絶・脳貧血・たちくらみなど多様に表現されます。一時的に心臓から脳への血流が途絶えて意識を消失します。通常は数分以内に回復します。心臓の不整脈によっておこる心原性失神のほか、起立性低血圧、頚部の圧迫や回旋、排尿・咳嗽・排便・息こらえ・嘔吐などに引き続いておこることもあります。
- 湿疹(小児)
-
乳児湿疹、おむつかぶれ、あせも、乾燥肌、水いぼ、ニキビ、アトピー性皮膚炎、じんましんなどお子様の皮膚トラブルに対応致します。 アトピー性皮膚炎に対してスキンケア指導(入浴方法、外用薬の使用方法など)を行います。
対応する診療科
- しびれ(全身)
-
全身のしびれには色々な原因がありますが四肢を含むしびれの場合はまず脳神経内科を受診しましょう。ストレスがあるときに過呼吸になると両手両足や口の周りにしびれ感が生じることがあります。過呼吸のために血中の二酸化炭素が減少しすぎて起こる現象で心配はいらないことがほとんどです。慌てずに紙袋などを口に当て、自分の呼気を再度吸い込むようにゆっくり呼吸しているとしびれが改善します(ペーパーバック法)。
- しみ
-
中部ろうさい病院では手術を主体とする美容外科・美容皮膚科は行っておりませんが、レーザーや軟膏(トレチノイン)を用いたしみ治療を形成外科で行っています。美容に関しては完全予約制となっておりますので、事前に電話でご相談ください。
- 斜視
-
左右の目の向きがそろっていない、同じものを見ていない状態です。一番多いのは目が外を向く外斜視ですが、内側を向く内斜視や上下方向にずれる上下斜視などもあります。治療法は原因によって異なります。強い遠視が原因で起きる調節性内斜視では眼鏡をかけることで改善が期待されます。斜視の角度が少ないものでは特殊な眼鏡をかけることもありますが、角度の大きい斜視では手術をして目の向きをそろえることがあります。
- しゃっくり
-
しゃっくりは何らかの刺激にょる横隔膜の痙攣です。その原因は通常は不明ですが飲み過ぎや食べ過ぎによる胃の膨満時に起こることが多いようです。持続性のしゃっくりは何らかの疾患が原因のことがあるので受診が必要です。
- 視力障害・視野障害
-
今まで見えていたのに突然見にくくなった、真っ暗で全く見えないなどの症状は視神経や網膜の炎症、血管障害の可能性があります。緑内障でも見える範囲が狭い・見えにくい・見えない部分が出現するなど症状があり、頭痛や眼痛、目の充血があれば早急に治療が必要です。両目で見える範囲が狭くなった、部分的に見えないところがあるなどの視野障害は脳腫瘍や脳梗塞など頭蓋内病変の可能性があります。
- 子宮筋腫
-
子宮筋腫は珍しくない腫瘍です。小さなものも含めると、30歳以上の女性の20~30%にみられます。筋腫は卵巣から分泌される女性ホルモンによって大きくなります。閉経すると、逆に小さくなります。複数個できることが多く、数や大きさはさまざまです。大きさやできる場所によって症状が違ってきます。できる場所によって、子宮の内側(粘膜下筋腫)、子宮の筋肉の中(筋層内筋腫)、子宮の外側(漿膜下筋腫)に分けられます。おもな症状は、月経量が多くなることと月経痛です。その他に月経以外の出血、腰痛、頻尿などがあります。また、不妊、習慣性流産等の原因になる場合もあります。
対応する診療科
- 子宮頸がん
-
子宮の頸部に発生するがんです。以前は発症のピークが40~50歳代でしたが、最近は20〜30歳代の若い女性に増えてきており、30歳代後半がピークとなっています。子宮頸がんのほとんどは、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスの感染が原因であることがわかっています。このウイルスは性的接触により子宮頸部に感染します。HPVは男性にも女性にも感染するありふれたウイルスであり、性交経験のある女性の過半数は、一生に一度は感染機会があるといわれています。しかしHPVに感染しても、90%の人においては免疫の力でウイルスが自然に排除されますが、10%の人ではHPV感染が長期間持続します。このうち自然治癒しない一部の人は異形成とよばれる前がん病変を経て、数年以上をかけて子宮頸がんに進行します。通常、早期にはほとんど自覚症状がありませんが進行するに従って異常なおりもの、不正出血、性行時の出血、下腹部の痛みなどが現れてきます。一次予防としてのHPVワクチン接種と、早期治療に結び付く二次予防としての子宮頸がん検診が重要です。
対応する診療科
- 子宮体がん
-
子宮の体部の内膜腺上皮から発生するがんです。最近我が国の成人女性に増えてきているがんのひとつです。発生には、多くは卵胞ホルモン(エストロゲン)という女性ホルモンが深く関わっています。卵胞ホルモンには子宮内膜の発育を促す作用がありますので、卵胞ホルモンの値が高い方では子宮内膜増殖症という前段階を経て子宮体がんが発生することが知られています。出産したことがない、肥満、月経不順(無排卵性月経周期)がある、卵胞ホルモン製剤だけのホルモン療法を受けている方などがこれにあたります。一番多い自覚症状は不正出血です。閉経後あるいは更年期での不正出血がある時には特に注意が必要です。
対応する診療科
- 子宮脱
-
骨盤臓器脱とは、骨盤内臓器が通常の位置よりも下垂する状態です。下垂する臓器によって呼び方が異なり、子宮脱、膀胱瘤、直腸瘤などに分類されます。骨盤底の支持機構の破綻が原因となります。出産経験者の約40%が何らかの骨盤臓器脱の症状を呈します。そのリスク因子となるのが経膣分娩や肥満です。症状として下腹部の違和感、尿失禁、便秘などを伴う場合があります。
- 子宮内膜症
-
子宮内膜またはそれに似た組織が何らかの原因で、本来あるべき子宮の内側以外の場所で発生し発育する疾患です。20~30代の女性で発症することが多く、そのピークは30~34歳にあるといわれています。子宮内膜症は女性ホルモンの影響で月経周期に合わせて増殖し、月経時の血液が排出されずにプールされたり、周囲の組織と癒着をおこしてさまざまな痛みをもたらしたりします。また、不妊症の原因にもなります。子宮内膜症ができやすい場所は、卵巣、ダグラス窩(子宮と直腸の間のくぼみ)、仙骨子宮靭帯(子宮を後ろから支える靭帯)、卵管や膀胱子宮窩(子宮と膀胱の間のくぼみ)などです。稀ではありますが肺や腸にもできることがあります。痛みの症状ですが、月経痛はもちろんのこと、月経時以外にも腰痛や下腹痛、排便痛、性交痛などがみられます。妊娠の希望のある内膜症患者さんの約30%に不妊があると考えられています。
- 歯根嚢胞
-
むし歯(う蝕)が進行し、歯髄に感染が起こり、それが歯根の尖端に波及すると、根尖性歯周炎が生じます。それが慢性化すると歯根肉芽腫(しこんにくげしゅ)や歯根嚢胞(しこんのうほう)ができます。 根管治療(歯の根っこの治療)で治癒することもあります。根管治療が奏効しない場合や根管治療ができない場合には、手術によって嚢胞の摘出を行います。原因歯の骨植が悪い場合には、嚢胞の摘出と同時に原因歯の抜歯を行います。原因歯の骨植が良い場合には、感染した歯根の尖端部の切除(歯根端切除術)とともに嚢胞の摘出を行います。
対応する診療科
- 四肢骨折
-
青壮年に多い労災事故、交通事故などによる四肢の骨折に対し、保存療法または手術療法どちらが望ましいかを検討した上で加療を行っています。手術適応のあるものには髄内釘、ロッキングプレートなどを用いた骨接合術を行い、より強固な内固定を得ることにより、早期のリハビリテーションを開始し、早期の社会復帰を目指しています。最新の知識をもとに、安全に行うことを心がけております。
対応する診療科
- 脂質異常症
-
一般に血清悪玉コレステロール値が140 mg/dL以上は高コレステロール血症、血清トリグリセリド値150 mg/dL以上は高中性脂肪血症となります。動脈硬化性疾患の予防のための各種ガイドラインでは、個々の患者さんの併発症や病状、年齢などによりその目標となる数値は異なります。比較的効果的な薬物が多く開発されており薬物治療にて基準値内に達成可能です。脂質異常症の治療により脳卒中や心筋梗塞などの発症抑制が明らかとなっています。
- 手根管症候群
-
手根管症候群では、手首の骨の隙間(手根管というトンネル)を通る正中神経が手根管内で圧迫され、特に親指、2指、3指のしびれや痛み、筋力低下が起こります。明け方に痛みで目が醒めることがあり、進行すると指先でつまむ細かい動作やペットボトルの蓋が開けにくいなどの症状も出現します。消炎鎮痛剤の内服や外用薬、装具などで治療しますが、これらが無効な場合は整形外科での日帰りでの手根管開放術を行います。利き手に症状がより強く現れることが多く、糖尿病などもともと末梢神経の脆弱性をきたす疾患をもつ人や、手首を屈曲する動作が多い仕事をするひとに発症率が高いことが知られています。
- 消化管がん(胃がん、大腸がんなど)
-
消化管(食道、胃、大腸)がんでは、内視鏡検査やCT、エコーなどを行い、がんの大きさや深さ(深達度)、転移の有無を調べ、進行度(ステージ)に応じて内視鏡的治療(内視鏡的粘膜切除術(EMR)、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD))、化学療法(抗がん剤、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害剤など)、放射線療法、手術療法といった治療を、外科や放射線科と密接に連携し、もっとも適切な組み合わせを選択・併用し、治療を行っています。
- 食道がん
-
食道がんは、初期にはほとんど自覚症状がありません。進行すると飲食時の胸の違和感、飲食物がつかえる感じ、体重減少、胸や背中の痛み、咳、声のかすれなどの症状が出ます。検査には、上部消化管内視鏡検査と上部消化管造影検査(バリウム透視検査)、CT検査、MRI検査、PET検査、腹部超音波検査、超音波内視鏡検査などを行います。治療法は、内視鏡的切除、手術、放射線治療、薬物療法があり、単独または組み合わせた治療を行います。
- 食物アレルギー(小児)
-
中部ろうさい病院小児科ではアレルギー検査の結果だけで除去するのではなく、必要に応じて食物経口負荷試験を実施して、必要最低限の除去で食事指導を行います。アレルギー検査ができない食品に関しては皮膚テストを行います。また、離乳食開始にあたり食物アレルギーなどが心配な方や離乳食の進め方に不安がある方には、離乳食指導も行います。
対応する診療科
- 心筋梗塞(急性心筋梗塞)
-
心筋梗塞は心臓に酸素を運ぶ冠動脈が詰まって血液が流れなくなり心筋が壊死してしまう病気です。 主な症状は胸痛です。胸が締め付けられるような圧迫感、息切れ、冷汗、吐き気などを訴える方もいます。 30分以上症状が継続することが多いです。早期に治療すれば救命可能な病気ですので緊急で病院を受診してください。
- 神経因性膀胱
-
排尿に関与する脳、脊髄、末梢神経の障害によって、膀胱の畜尿機能、排尿機能に異常が生じた状態を神経因性膀胱と言います。畜尿(尿を貯める)機能の異常では尿漏れ、頻尿等を起こし、排尿(尿を排出する)機能の異常では排尿困難を起こします。神経因性膀胱を起こす病態としては脳の障害では脳出血、脳梗塞、脊髄の障害では脊髄損傷・脊髄炎、末梢神経の障害としては糖尿病による神経障害や骨盤内手術後の神経損傷があります。
- 心房細動
-
心房細動は心房で生じた異常な電気興奮によりおこる不整脈で、主な症状は動悸、息切れ、胸の違和感などです。心房細動になると心房の中で血栓ができやすくなり脳梗塞を発症するリスクが大きくなるため、原則生涯にわたって抗凝固剤の内服が必要です。また、心臓に負担がかかり心不全を発症することもあります。早期に診断ができれば、体に負担の少ないカテーテル治療により根治することもできるようになってきています。早めに受診をしてください。
- 小児保健
-
乳児健診:1ヶ月健診、10ヶ月健診以外にも 保健所での健診で小児科への受診を勧められた場合もご相談ください。 予防接種:各種予防接種に加え、早産児やダウン症児などのシナジス注射も行います。
対応する診療科
- 情緒不安定
-
極端に気持ちの浮き沈みが激しい、怒りっぽい、感情表現が乏しい、無関心などの気分変調は双極性障害など精神障害によるものだけではなく、認知症やパーキンソン病、慢性硬膜下血腫などの神経疾患、アルコール、薬物などの影響、腎不全・肝不全などの全身疾患が原因のこともあります。女性では月経前症候群(PMS)として不安やいらいらが強く認められることがあります。
- 褥瘡
-
形成外科では主に下半身麻痺の車いすの方のとこずれについて診療を行っています。手術加療も行いますが、長時間車いす生活の方の褥瘡は環境改善やプッシュアップ動作などの生活生活改善を行うことが重要で、皮膚排泄ケア(WOC)認定看護師とともに再発のしにくい治療を目指しています。
- 女性に起こりやすい病気のスクリーニング
-
乳腺疾患の多くや子宮・卵巣の異常が女性に多いことは当たり前ですが、膠原病(リウマチ関連)や甲状腺などの内分泌疾患、骨粗鬆症などあきらかに男性よりも女性に起こりやすい疾患があります。女性外来では患者さんの訴え・症状から、女性に多い疾患のスクリーニングが可能です。結果により女性スタッフが行う乳腺検診・婦人科検診をご案内することも可能です。
- 縦隔腫瘍
-
右と左の肺に挟まれた部分を縦隔といい、上縦隔、前縦隔、中縦隔、後縦隔に分類されます。これらの縦隔に発生する腫瘍のことを縦隔腫瘍といい、その中で最も多いものが胸腺腫です(約40%)。縦郭腫瘍は、多くの場合症状がありませんが、腫瘍が大きくなるにつれて、胸の痛みや違和感、呼吸困難や嗄声(声のかすれ)を認めることがあります。腫瘍の種類によって治療方針は変わりますが、手術を行うことが多いです。
- 重症筋無力症
-
重症筋無力症とは、末梢神経と筋肉のつなぎめで神経から筋への指令を伝える物質(アセチルコリン)が不足してしまうために、脳からの運動指令が伝わらず脱力のおこる自己免疫疾患です。瞼が下がる(眼瞼下垂)や物が二重に見える(複視)など眼の筋肉から発症することが多く、四肢や首の筋力低下が加わることもあります(全身型)。鼻声や、咬む、飲み込む力の疲労のため嚥下障害が起こることもあります。朝は調子が良くても、すぐ疲労して悪化するという時間によって症状が変動することが特徴です。重症筋無力症にはステロイドホルモン剤や免疫グロブリンの大量投与が有効です。眼筋型と全身型があり、全身型の一部の症例では免疫に関する臓器である胸腺を外科的に摘出することもあります。(厚労省指定難病)
- 循環器疾患(小児)
-
先天性の心臓病、不整脈、川崎病などの疾患の心臓エコー検査や心電図検査などを行います。乳児健診や学校の検診で異常を指摘された時の検査も行います。
- 上肢切断(能動義手・筋電義手)
-
労災保険では、平成25年以降労働災害による上肢切断者に対して、電気の力で動かす筋電電動義手を支給する制度ができました。中部ろうさい病院リハビリテーション科では能動義手製作訓練を積極的に行うと同時に、適応のある患者さんには評価用筋電義手を無料で貸し出して、病院だけでなく自宅での練習に使用していただき、労働局と協力して、支給の必要性の判断を行っています。また、労働災害以外の上肢のない方(成人および小児の先天性上肢欠損者を含む)にも筋電義手が必要と思われる場合は、同様の練習の場を提供して、障害者総合支援法に基づいた自治体への意見書を作成しています。
対応する診療科
- 腎がん
-
腎臓は背中の直下に左右1つずつある重さ約150gmのそら豆状の臓器で、主な働きは尿をつくり体内の老廃物を排泄することです。腎がんは尿生成を行なう腎実質にできるがんです。症状には肉眼的血尿、腰背部痛、腹部腫瘤がありますが、最近は健康診断(CT、超音波検査)で早期発見されることが多いです。腎がんに有効な薬も複数ありますが、早期発見し手術で腎臓全体もしくはがんを含めた腎臓の一部を摘出するのが根治するための唯一の治療法です。
対応する診療科
- じん肺
-
準備中
- 腎不全(末期)
-
原因によらず、腎機能の低下が進行した状態が末期腎不全です。おおよそeGFR10ml/min/1.73㎡未満になると尿毒症の症状が強く出やすくなります。症状はとても多彩で、動悸息切れ・貧血・むくみ・吐き気や食欲低下・かゆみ・疲れやすさなど様々です。体内にたまった老廃物を除去し、症状を改善させるには腎代替療法(透析か腎移植)が必要です。人工透析療法(腹膜透析や血液透析)、腎移植(献腎移植や生体腎移植)といった治療法があり、基礎疾患や年齢、生活スタイルなどを考慮しながら相談してどの治療が最適かを決めていきます。
- 女性医師・スタッフに相談したい時
-
症状があっても「何科を受診すればよいかわからない」、健康不安があっても「ちょっと男性医師には相談しにくい」と感じる場合には女性総合外来へ相談してください。原則的には女性総合外来はどのような主訴にも対応し、治療の方向性をアドバイスします(治療は該当科をご紹介します)。
対応する診療科
- 膵がん(消化器内科)
-
膵がんは初期には無症状のことが多いため、早期には極めて発見しにくいがんです。各種画像検査を行い、必要に応じて超音波内視鏡下穿刺吸引細胞診(EUS-FNA)を行い、診断を確定していきます。治療は手術が第一選択で、病変の拡がりや患者さんの状態を見極め、手術が可能かどうかを評価します。進行した状態であっても、以前は選択肢が少なかった抗がん剤も、nab-PTX(商品名:アブラキサン)、Nal-iri(商品名:オニバイド)といったくすりや、免疫チェックポイント阻害剤など治療の選択肢が増え、長期生存が見込めるようになってきています。
- 膵がん(外科)
-
膵がんは膵臓にできるがんで、悪性腫瘍です。腹痛、食欲不振、腹部膨満感、黄疸、腰痛、背部痛などが症状です。糖尿病の発症や増悪がみられることがあります。血液検査、腹部超音波検査、CT検査、MRI検査、PET検査、超音波内視鏡検査等を行います。治療には、手術、薬物療法、放射線治療があります。手術のみ、もしくは手術と薬物療法、放射線治療を組み合わせた治療(集学的治療)を行います。切除できない場合は、主に薬物療法や薬物療法と放射線治療を組み合わせた治療を行います。
- (中枢性)睡眠時無呼吸症候群(CSAS)
-
気道の閉塞によっておこる閉塞性睡眠時医無呼吸ではなく、脳の働きの低下から睡眠時に無呼吸のため低換気状態となり血中の二酸化炭素濃度が上昇してしまうことがあります。脳変性疾患であるパーキンソン病や進行性核上性麻痺、認知症のひとつであるびまん性レビー小体病、多系統萎縮症などに多く、突然死の原因となります。
- 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)
-
閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)とは睡眠中に断続的に無呼吸(むこきゅう:10秒以上続く気流停止)を繰り返し、その結果、日中の眠気などの症状に加え呼吸循環系への障害をきたす疾患で、中年男性のいびきをかく人や肥満者に多くみられます。 治療としては、肥満のある人では減量が基本的治療として重要ですが、経鼻式陽圧呼吸(NCPAP)(けいびしきようあつこきゅう)や、口腔内装具(マウスピース様の装置)により下顎を前方に位置付けて上気道を拡張させ治療する歯科的治療が効果的であることがわかっています。
- 頭痛
-
頭痛には脳腫瘍・脳卒中(くも膜下出血・脳出血・脳梗塞など)の器質的疾患に伴う頭痛と、脳などの組織に異常がない器質的疾患に伴わない頭痛(機能的頭痛)に分類されます。発熱があり嘔吐を伴う頭痛、首が痛くて顎の先が胸につかない後頚部痛などの場合は髄膜炎の頭痛を疑います。機能的頭痛の大半は肩こりなどから誘発される筋緊張性頭痛で、頭全体の締め付けられるような痛みが出現します。片頭痛は脳表面の硬膜血管の拡張を原因とする頭痛で、目のチラツキや視野異常などの前駆症状を伴うことがあり血管性頭痛と呼ばれます。頭痛の診療には器質的頭痛の否定が必要です。普段からの頭痛の有無に関わらず突然の「今まで経験したことのない痛み」や手足のしびれ・運動麻痺・嘔吐を伴う、視野が狭い・視力が急におちるなどの症状がある場合は速やかに脳神経内科・外科、救急外来への受診が必要です。
- 性器出血(不正出血)
-
月経とは無関係な膣出血は子宮頸がん・子宮体がん、卵巣がんなど婦人科系の悪性腫瘍の初期症状のことがあるので注意しましょう。女性ホルモン分泌に変化のおこる更年期や強いストレスでも不正出血がおこることがあります。
- 咳
-
風邪などによる咳は、通常であれば数日でおさまる場合がほとんどです。2週間以上も咳が続く、咳で眠ることができないなどの場合は風邪以外の原因かもしれないので受診が必要です。
- 背中の痛み
-
骨の異常・筋肉疲労による筋肉痛、神経痛などで痛みが生じます。膵臓がんや肺がんの症状のこともあります。突然の激痛や、強い痛みが続く場合は狭心症や大動脈解離など危険な病気の可能性もあり早めの受診が必要です。
- 性器感染症(前立腺炎、精巣上体炎)
-
前立腺、精巣上体に細菌等が侵入して生じた感染症です。急性前立腺炎は、排尿時痛、排尿困難、頻尿、発熱等の症状で発症します。また急性精巣上体炎は陰嚢の腫大、疼痛、発熱等で発症します。どちらの病気も抗生剤で治療を行います。また男性のみに生じる病気で、性行為を介して感染する場合もあり注意が必要です。
対応する診療科
- 正常圧水頭症
-
歩行障害、認知機能障害、尿失禁が主な症状です。画像診断および髄液検査(タップテスト)で臨床診断が確定され、外科的手術(シャント手術)を行います。脳外科と脳神経内科が連携して適切な診断・治療を行います。
- 脊髄損傷後四肢体幹麻痺
-
頚髄損傷による四肢麻痺、および胸腰髄損傷による対麻痺になった患者さんがリハビリテーション目的に入院されます。高位頚髄損傷の場合は人工呼吸器の外れた時点で、リハビリテーション科に入院していただいています。多くの患者さんにおいて障害が重いため、理学療法士・作業療法士・言語聴覚療法士・看護師らと密に連携したリハビリテーションを提供しています。また、麻痺した患者さんがなりやすい褥瘡・仮骨性筋炎・神経障害性疼痛などにはさまざまな検査、評価をおこなった上で、患者さんに適した治療を選択します。手術後の脊椎評価は整形外科のサポートを受けることができます。
対応する診療科
- 脊髄損傷後神経因性膀胱
-
脊髄損傷が原因となり排尿障害を来します。リハビリテーション科では膀胱造影・膀胱内圧測定などを組み合わせたウロダイナミクススタディーを実施し、泌尿器科と連携することにより内服薬の調整をしています。また泌尿器科で行われている膀胱へのボツリヌストキシンの施注前後にこの評価を行うことによって、適切で総合的な排尿管理法を提案しています。
- 脊髄損傷後直腸機能障害
-
脊髄損傷後には、排尿と同様に便排出障害や便失禁を来すことがしばしばみられます。緩下剤の内服や浣腸療法では症状が改善しないことや介護する側の労力を要することがしばしばみられますが、コロプラスト社が開発したペディスティーンを使用した洗腸療法を導入することにより、多くの脊髄損傷患者さんで排便対処時間の短縮や便失禁の改善などが得られています。
対応する診療科
- 摂食障害
-
摂食障害とは、過食・拒食など食事行動の異常が続き、体重や体型のとらえかた(ボディイメージ)などを中心に心と体の両方に影響が及ぶ病気の総称です。やせや栄養障害、嘔吐などの症状によって身体の合併症がおこりときには生命の危険に陥ることもあります。10代から20代の女性に多いと言われていますが年齢や性別に関わらず誰にでもおこる可能性があります。
- 切迫早産
-
切迫早産とは早産(22週0日~36週6日までの出産)となる危険性が高いと考えられる状態のことをいいます。子宮収縮が規則的かつ頻繁におこり、子宮の出口(子宮口)が開き、胎児が出てきそうな状態のことです。切迫早産の治療では、子宮口が開かないようにするために、子宮収縮を抑える目的で子宮収縮抑制薬を使用することがあります。切迫早産の原因の一つでもある細菌による感染が疑われれば抗菌薬を使用することもあります。子宮収縮の程度が軽く、子宮口があまり開いていない場合は外来通院による治療でもいいのですが、子宮収縮が強く認められ、子宮口の開大が進んでいる状態では、入院して子宮収縮抑制薬の点滴治療を考慮します。
対応する診療科
- ぜんめい(喘鳴)
-
呼吸時の喘ぐような音を「ぜんめい」と呼びます。吸気時のあえぐような音を吸気性ぜんめい、吐く時を呼気性ぜんめいと言いますが、いずれも気道(息の通り道)になんらかの閉塞があることを意味します。あえぐような呼吸が続く、意識レベルの低下、顔面や舌の腫れを伴う場合などはすぐに救急外来を受診するべきです。
- 舌痛症
-
舌痛症(ぜっつうしょう)は舌に炎症や潰瘍などの明らかな病変がなく、その色調や機能も正常ですが、患者が舌に慢性的なひりひり感、ぴりぴり感、灼熱感(しゃくねつかん)などの痛みを訴える疾患です。貧血に伴う舌炎による舌痛、糖尿病、薬物などによる口腔乾燥により二次的に生じる舌痛、歯列不正、咬耗に伴う歯および補綴物鋭縁、舌癖による舌痛、カンジダ症による舌痛などと区別する必要があります。中高年の女性に多く、食事中や何かに熱中している時には痛みを感じないことが多いのが特徴で、歯科心身症の代表的な疾患です。 治療としては、さまざまな方法が試みられますが、現在、最も有望な治療法は抗うつ薬を中心とした薬物療法です。
- 舌がん
-
口腔がんは、口唇がん、舌がん、口底がん、歯肉がん、頬粘膜がん、硬口蓋がんなどに分けられます。これらのうち、舌がんの発生頻度がもっとも高く、口腔がんの約40%を占めます。そのほかには唾液腺から発生するがんなどもみられます。 悪性腫瘍は、(1)病気の進行が速く、できもの(潰瘍、腫瘤)が速く大きくなる、(2)できものの周りが硬い、(3)周囲と癒着していて、境界がはっきりしない、(4)他の部位に転移する、などの性質があります。病期が進むにつれて咀嚼や嚥下、発音が障害されたりします。また、頸部のリンパ節に転移します。さらに進行すると、肺、骨、肝臓など他の臓器に転移し、全身的な症状をおこすようになります。
対応する診療科
- 前立腺がん
-
前立腺は男性にしかない臓器で精液の一部を産生し、膀胱の直下の骨盤の奥深いところに位置しています。この前立腺に発生するがんが前立腺がんです。前立腺がんの症状には排尿困難、血尿、腰痛等ありますが症状が出現してからでは手遅れになることが多いです。手遅れにならないためには前立腺がん検診(PSA検査)を受け早期発見、早期治療が大切です。前立腺がんの治療には手術療法、放射線療法、ホルモン療法と三本の柱があり治療しやすいがんと言えます。
対応する診療科
- 前立腺肥大症
-
男性は40歳代に前立腺の一部にしこり(結節)が作られ、後にこの結節が大きくなり(腺腫)、前立腺の中心を走る尿道を圧迫し、排尿困難、頻尿等様々な症状を引き起こします。飲酒後全く尿が出なくなり下腹部が張って苦しくなり、夜間病院に駆け込むことは前立腺肥大症の患者様にはよくあるエピソードです。治療には薬物療法(内服薬を飲む)、手術療法(経尿道的手術)等があります。
対応する診療科
- 総胆管結石
-
肝臓で作られる胆汁が流れている総胆管に結石ができ、大きくなると胆管をふさいでしまい、細菌感染や膵炎などを引き起こすおそれがあり、総胆管結石は緊急の治療が必要となることも多い病気です。内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)を行い、結石の大きさ、個数を確認し、内視鏡的乳頭括約筋切開術(EST)や内視鏡的乳頭大口径バルーン拡張術(EPLBD)で結石を取り除きます。
- 鼠径ヘルニア
-
鼠径部(脚の付け根)に生じるヘルニアの総称が鼠径ヘルニアです。一般的に"脱腸"と呼ばれている病気です。腸や腸を覆う脂肪組織、卵巣、膀胱などが腹壁に生じた欠損部から飛び出します。内臓の脱出により鼠径部に膨らみができ、違和感や不快感、痛みを伴うこともあります。多くの場合は腹圧がかかったときに飛び出し、仰向けになると引っ込みますが、放置すると次第に大きくなっていき、内臓がはまりこんで元に戻らない状態(嵌頓)となることがあります。治療は手術です。腹腔鏡手術も行われています。