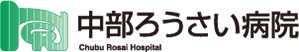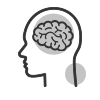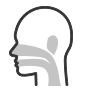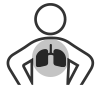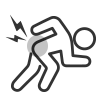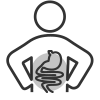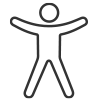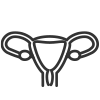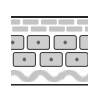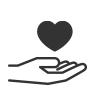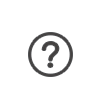症状/疾患・部位 からさがす
- TOP
- 症状/疾患・部位 からさがす
- 「か行」の症状/疾患
「か行」の症状/疾患
- 介護の悩み
-
介護に関わる問題は非常に大きな健康不安の原因のひとつです。特に認知症の介護には非常に大きな精神的・身体的負担を伴います。介護が原因で体調不良や精神的不調を起こし、うつ・神経症を発症することも珍しくありません。介護は女性のみの問題ではありませんが、実際はまだまだ女性が担う場合が多いのも事実です。女性外来では介護の悩みについてのアドバイスをおこなっています。ご本人の症状ばかりでなく、介護対象者が利用できる福祉制度説明などや専門の医療相談員との連携も可能です。
- 顔の痛み
-
顔面の疼痛は三叉神経痛と呼ばれます。原則片側だけに、洗顔や髭剃りなどの時に瞬間的な強い痛み(電撃痛)が起こります。痛みのコントロールには抗てんかん薬が有効ですが、難治例では脳外科的に除圧術を行う場合もあります。副鼻腔炎(蓄膿症)でも頭痛や顔の鈍痛がおこることがあります。帯状疱疹が三叉神経領域に起こり激しい痛みを伴うことがあります。
- 過換気症候群
-
ストレスがあるときに過呼吸になると両手両足や口の周りにしびれ感が生じることがあります。過呼吸のために血中の二酸化炭素が減少しすぎて起こる現象で心配はいらないことがほとんどです。慌てずに紙袋などを口に当て、自分の呼気を再度吸い込むようにゆっくり呼吸しているとしびれが改善します(ペーパーバック法)。
- 肩こり・首のこり
-
長時間同じ姿勢でいると後頚部や肩甲骨周囲の筋肉が凝り固まって緊張し、頭痛やめまいの原因になります。猫背やストレイトネックなど体型から肩こり・首こりが起こりやすい人もいますが、スマホを見続ける、不適切な姿勢でPC作業を長時間おこなうなどが誘因になります。肩こり・首こりからの頭痛やめまいは片頭痛とは異なり、ストレッチ、運動、温めることで軽快するのが特徴です。
- かゆみ
-
かゆみは非常に不快な感覚です。皮膚炎などの皮膚の病気から起こるものが一般的ですが、食品や薬などのアレルギー反応、胆嚢や肝臓の病気で黄疸が起こると全身にかゆみがでます。慢性腎不全、鉄欠乏性貧血でもかゆみが生じることもあります。ストレスが関係して皮膚のかゆみがでることもあるようです。
- 関節痛
-
微熱を伴う関節痛はリウマチや膠原病の症状である可能性があります。レントゲン写真や血液検査で診断をします。痛風発作の痛みは発赤や腫れを伴い足の指、ひざ関節などによくみられます。インフルエンザやコロナなどのウイルス感染症では発熱に節々の痛みや筋肉痛を伴います。2から5指の第一関節が変形して曲がるヘバーデン結節は40代以降の女性に多い変形性関節炎です。
- 海綿状血管腫
-
脳の中に発生する海綿状に膨らんだ異常血管のかたまりを海綿状血管腫といいます。 無症状のものから、出血を繰り返し痙攣を発症することもあり、適切な治療が必要です。専門医のいる病院受診をお勧めします。
- 過活動膀胱
-
過活動膀胱は症状によって診断される症候群(病気)です。すなわち、尿意切迫感(急に強い尿意を催す)が必須の症状で、頻尿(何回も排尿する)や夜間頻尿(就寝後何回も排尿に起きる)を伴い、場合によっては切迫性尿失禁(急に強い尿意を催しトイレまで我慢できずに尿を漏らす)を合併します。つまり、尿意切迫感があれば、男性でも女性でも過活動膀胱が疑われます。治療法としては骨盤底筋体操を含めた行動療法、薬物療法(薬の内服)があります。
対応する診療科
- 下肢切断者(義足)
-
下肢切断の原因は、従来は外傷が主体でしたが、最近では糖尿病・閉塞性動脈硬化症・骨軟部組織腫瘍・細菌感染症などが原因になることが多くなっています。また中高齢者の患者さんも増えています。切断患者さんには早期からリハビリテーションを行って切断部分の形を整え、仮義足を作成します。最近は見た目より機能を重視した義足が選択される場合が多くなり、切断部分にも負担が少なく、かつ切断した足の長さに適したソケット(切断部分を包んで義足をつなぐ部分)が選択できるようになりました。また、義足の関節部分にあたる膝継手や足継手においても歩行能力をより良好にするためのものを選択できるように努めています。
対応する診療科
- 下垂体腫瘍
-
下垂体と呼ばれるホルモン産生する部位に腫瘍が生じることがあり、下垂体腺種と呼ばれる良性腫瘍が大部分を占めます。鼻腔より細径の内視鏡を挿入し下垂体病変へ到達します。脳腫瘍と同様に様々な治療法があり、適切に判断します。内視鏡手術ではより視野が広く取れるため低侵襲で安全な手術が可能です。
- 花粉症
-
くしゃみ、鼻みず、鼻づまりが主な症状です。スギ、ヒノキなどの花粉やダニ、ハウスダストやペットなどが原因となります。 中部ろうさい病院耳鼻咽喉科では内服治療で効果が乏しい人に対してCO2レーザーによる粘膜焼灼や全身麻酔下で選択的後鼻神経切断術を行います。
- 肝硬変
-
肝硬変とは肝臓に長く炎症がおこることから肝臓が硬くなる病気です。ウイルス性肝炎、脂肪肝、お酒の飲み過ぎ、自己免疫性肝炎などが原因です。症状が進行すると黄疸や腹水、浮腫、食道静脈瘤や静脈瘤の破裂による吐血、肝性脳症による意識障害などが出現し生命予後に関わります。
- 肝細胞がん
-
肝細胞がんのハイリスクグループである慢性肝炎、肝硬変の患者さんは、定期的な画像診断(腹部超音波検査、造影CTなど)を行うことで、肝細胞がんの早期発見、早期診断が可能です。患者さんの状態、がんの大きさ・個数、肝臓の予備能などを考慮し、最適な治療法を選択していきます。治療法として、外科的肝切除、経皮的局所療法(ラジオ波焼灼術;RFA、エタノール注入療法;PEIT)や、肝動脈化学塞栓術(TACE)などに加え、分子標的薬(レンバチニブ、ソラフェニブ、レゴラフェニブなど)、免疫チェックポイント阻害薬(アテゾリズマブ+ベバシズマブ併用療法)による全身化学療法を行っています。
- 間質性肺炎
-
準備中
- 眼瞼下垂
-
加齢とともに瞼がさがってくる状態で、40歳以上の日本人は多かれ少なかれ全員下がるとも言われています。見えにくさや視野の改善、眠たそうな見た目の整容面の改善のために手術を行っています。また副次的に肩こりや頭痛の原因となっていることもあり、手術を行うことでそれらの症状が改善することもあります。加齢以外に重症筋無力症・動眼神経麻痺など脳神経内科疾患の症状で眼瞼下垂がおこることがあります。
- 外傷(一般外傷)・やけど
-
表在性の外傷の治療については主に形成外科が行っています。やけどについては適切な湿潤療法を用いて痛みが少なく傷あとがきれいになるような治療を心がけています。
- 顎関節症
-
顎を動かしたときの痛みや関節部の雑音、さらに顎の運動がスムーズでなく、 ひっかかったような異常な運動をする、などの症状がみられる症候群を顎関節症(がくかんせつしょう)といいます。顎を動かすと顎関節が痛んだり、雑音がしたり、顎関節周囲の筋肉や靭帯 (じんたい) の圧痛など、顎の運動異常を主症状とし、重症になると開口障害や咀嚼障害をひきおこし、首や肩に症状が出ることもあります消炎鎮痛薬(しょうえんちんつうやく)、各種マウスピースによる保存療法が主体です。筋のマッサージや開口訓練等のリハビリを継続的に行うことも治療法の一つです。
対応する診療科
- 顎変形症
-
顎変形症(がくへんけいしょう)には、(1)上顎前突症(じょうがくぜんとつしょう) (2)上顎後退症(じょうがくこうたいしょう) (3)下顎前突症(かがくぜんとつしょう) (4)下顎後退症(かがくこうたいしょう)のほか、咬合時に上下の前歯にすき間を認める開咬症(かいこうしょう)や、下顎骨が左右非対称で、このため顔も非対称となる顔面非対称(がんめんひたいしょう)などの異常があります。歯並びの治療だけでは改善しない骨格の異常には顎矯正手術(がくきょうせいしゅじゅつ)の適応となります.手術は、多くの場合、口の中の切開によって行われるので顔に傷がつくことはありません。異常のある顎骨を骨切りし、正常な位置まで移動させてプレートやスクリューなどで固定します。
対応する診療科
- 顎骨壊死
-
ビスフォスフォネートは骨粗鬆症、乳がん、前立腺がんなどの骨転移に対して投与され、がんによる骨痛の軽減、転倒による骨折の予防などに有効性の高い薬剤です。しかし、副作用として、口腔感染を契機に顎骨の壊死が生じることがあります。症状は、持続的な骨露出、歯肉の腫脹や排膿などですが、痛みを伴わず無症状のこともあります。進行すると痛みや感染が増悪し、病的骨折をおこしたり、皮膚瘻孔を形成します。 なお、ビスフォスフォネート以外の骨吸収抑制薬でも同様の症状を起こすことが知られています。
対応する診療科
- 顔面骨骨折
-
手足の骨折は整形外科、顔面の骨折治療は形成外科で行います。車の安全性能が上がり、バイクのヘルメット装着率が上がったため、全国的に以前よりは顔面の骨折発生頻度は減っているようですが、最近はお年寄りの自転車転倒やスポーツ時の外傷などにより起こることも多く、形成外科では症状に応じてできるだけ目立たない切開より骨折整復を行い、同時に傷跡の目立ちにくい縫合や術後のケアを行っています。
対応する診療科
- 顔面神経麻痺
-
脳梗塞やの脳出血などの病気で片側の瞼が下がる、口が歪むなどの症状が出現することがありますがこれは顔の筋肉の麻痺であり通常手足の麻痺も伴います。そのような脳の症状ではなく顔の筋肉を動かす末梢神経である顔面神経の炎症によって顔筋麻痺がおこります。大抵は突然発症で、冷たい風に長時間あたる、氷枕が冷たすぎるなどが誘因になることもあります。ビタミン剤や重症例ではステロイドホルモン剤で治療します。帯状疱疹(みずぼうそう)のウイルスが原因の顔面神経麻痺(ハント症候群)では耳介に水疱が現れ、抗ウイルス薬を使用することもあります。
- 胸痛
-
胸の痛みは心臓や肺の疾患の症状として頻度が高いものです。緊急性の高い病気のことが多いので、痛みが強い、長く続くなどの場合はできるだけ早く受診してください。慢性胸痛は食道に胃液が逆流する食道炎が原因かもしれません。
- 起立性低血圧
-
急に立ち上がったときに感じるふらっとしためまいをたちくらみといいます。通常はわずかな時間で治ります。立ちくらみの多くは臥位や座位から立ち上がった時に起こる脳貧血(起立性低血圧)が原因です。体位の変化に血圧調整がついていかないため立ち上がった時に血圧が急に下がります。加齢、糖尿病やパーキンソン病などの自律神経障害を伴う疾患で認められます。小児や若年者でも立っていると気分が悪くなる、たちくらみがするなどの「調節性障害」を起こすことがあり、自律神経のはたらきがうまくいかない症状です。血圧調節に関わる自律神経失調や心因性などいろいろな原因があります。
- 気管支喘息
-
準備中
対応する診療科
- 気管支喘息(小児)
-
小児科ではアレルギー検査や環境整備の指導、呼吸機能検査が可能なお子様に対しては、定期的な検査で健康な日常生活が送れるようにコントロールを行います。 吸入器の貸し出し(原則、吸入器購入までの1週間程度)も行います。
- 気胸
-
気胸(自然気胸ともいいます)は、“肺に穴があいて肺がつぶれる”病気です。ほとんどの患者さんは肺の表面にある肺のう胞(ブラともいいます)の破裂が原因で気胸になります。肺がつぶれるため、胸や背中の痛み、咳、息切れなどの症状が出現します。初めての気胸であり程度も軽い場合は、安静にして経過をみることが多いですが、そうでない場合は胸の中(胸腔)にドレーンという管を入れることもあります(胸腔ドレナージ)。胸腔ドレナージを行っても良くならない場合は、手術(胸腔鏡というカメラを使用した手術)が必要になります。
- 急性期脳梗塞
-
急性発症の脳梗塞のうち、外科治療が必要な場合、脳神経外科で対応します。急性期治療には大きく脳血栓溶解療法(tPA)と脳血栓回収療法があります。これらの治療は従来の内科治療より機能回復に優れているとされています。中部ろうさい病院は一次脳卒中センターの認定を受けており急性期脳卒中の治療を常時行える体制を整えています。
- 急性腎障害
-
急性腎障害とは、数時間〜数日の間に急激に腎機能(尿をつくり、老廃物を排泄するはたらき)が低下する状態です。無症状の人もいますが、重症になると尿の減少、むくみ、食欲低下、全身倦怠感などを自覚することがあります。採血では血中尿素窒素(BUN)、血清クレアチニン(Cr)、カリウム(K)などが急に上昇します。腎臓自体に原因がある場合と、脱水や尿路の閉塞など腎臓以外に原因がある場合にわかれます。診断したら急いで原因を突き止め、その治療を行います。腎機能の回復は、腎障害の原因や程度、合併症の状況によって異なるため、腎障害が残って慢性腎臓病や末期腎不全に移行してしまうケースもあります。
対応する診療科
- 狭心症
-
狭心症は心臓に酸素を運ぶ冠動脈の内腔が狭くなり詰まりかけている病気です。主な症状は、重たいものを持ったとき、階段を歩いたときなど労作によって起こる胸痛です。安静にすると改善します。心筋梗塞と違い、心臓の筋肉は壊死していませんので早期に治療を行うことで健常な方と同じような生活が遅れます。早めに病院を受診してください。
- 強迫性障害
-
「何度手を洗っても汚い気がする」、「戸締りや火の始末を何度も確認せずにいられない」などどうしてもぬぐえない不安や強いこだわりのために生活が不便になっている場合は強迫性障害の症状の可能性があります。こころの病気であることに気が付かないひとも多いのですが、治療によって改善する病気です。「せずにいられない」「不安が頭からはなれない」ことでつらさや不便を感じる時には受診が必要です。
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
-
筋萎縮性側索硬化症(ALS)とは脳および脊髄の運動神経細胞が変性するため、四肢・のど・舌の筋肉が徐々に萎縮し動かなくなる病気です。筋力低下だけではなく飲み込みにくい・痰が出しにくいなどの症状が先行する場合もあります。呼吸筋の麻痺が進行すると人工呼吸器の装着が必要になります。残念ながら現在は根治させる治療法がなく、神経細胞保護剤による進行抑制や痛み・呼吸苦への対症療法が治療の中心になります。(厚労省指定難病)
- ギラン・バレー症候群(GBS)
-
GBSとは風邪症状や下痢症状の治った後、主に運動神経を攻撃する自己抗体が血液に出現し、末梢神経の炎症が起こり手足の運動麻痺をきたす疾患です。数日・数週間で自然回復する例もありますが、重症例では呼吸筋麻痺や重度の不整脈を起こすことがあり、歩行障害などの後遺症が残る場合もあります。早期診断・治療(免疫グロブリン投与・血漿交換)が非常に重要です。神経伝導検査や髄液検査を行い診断します。
- くも膜下出血
-
くも膜下出血の多くは頭蓋内血管に形成された瘤(脳動脈瘤)が破裂することにより生じます。緊急性の高い疾患で、再破裂予防のための処置を行う必要があります。外科治療には開頭手術による動脈瘤頚部クリッピング手術と血管内治療(カテーテル治療)によるコイリング手術があります。
対応する診療科
- 血尿
-
真っ赤な尿(肉眼的血尿)は尿路の悪性腫瘍(がん)や結石、膀胱炎などの原因が考えられます。見た目の尿の色調に異常がなくても、健診などの検査で指摘された血尿(顕微鏡的血尿)を起こす種な病気は腎臓の糸球体の異常が原因かもしれません。尿蛋白の異常がないかどうかも重要です。
- 倦怠感・疲労感
-
十分な休息を取っても解消されない日常生活に支障をきたす倦怠感・だるさ・意欲低下などが半年以上継続する場合が受診のめやすになります。それ以外でも発熱やむくみ、関節痛、体重減少などを伴う場合は早めにまずはかかりつけ医に相談しましょう
- 頚椎症性神経根症・頚椎椎間板ヘルニア
-
加齢に伴う頚椎変性(骨棘の形成)や椎間板の膨隆(ヘルニア)によって,椎間孔(神経の枝の出口)が狭くなり神経根が圧迫されて生じます。 片側の上肢のしびれ・痛み(多くは頚椎を後屈すると悪化),ときに上肢の筋力低下が認められ、頚椎MRI等で椎間孔の狭窄所見が診断の根拠になります。鎮痛剤の内服,ブロック加療,手術の順にリスクの低いものから段階を踏んで治療を行います。ブロック加療としては神経根ブロックや椎間板ブロック,手術療法としては人工椎間板置換術や前方椎体固定術などがあります。脳神経疾患(脳梗塞・末梢神経障害)などとの鑑別は脳神経内科で行います。
- 頚椎症性脊髄症
-
加齢に伴う頚椎変性(椎間板の膨隆,黄色靭帯の肥厚など)によって,頚椎の脊柱管の中にある脊髄本幹が圧迫されて生じます。 上肢や下肢のしびれ・運動障害といった症状に加え,頚椎MRIで脊髄の圧迫所見により診断します。しびれのみの場合は経過をみることが多いですが,進行してボタン・箸・書字など手指巧緻運動の障害や,歩行時のふらつきなど下肢運動障害が出てくると脊柱管を拡大する手術療法(椎弓形成術など)を考慮することになります。
- ケロイド
-
外傷や手術後の傷跡のケアについて、薬物療法やテーピングなどによる症状の緩和や改善を指導し、必要に応じて手術療法も行っています。また再発しやすいケロイドに対しても薬物療法のみではなく、放射線科の協力のもとに放射線治療も併用し再発防止を目指して手術も行っています。
- 下痢
-
便の水分が異常に増え液状の状態が「下痢」、通常より少し柔らかい状態を「軟便」といいます。いわゆる食あたり・水あたりのほか、脂肪分や糖分が多い食品を食べ過ぎた時などに消化不良をおこすことがあります。乳製品が体質的にあわないひと(乳糖不耐)が日本人には多く慢性下痢の原因になります。薬やストレスが原因のこともあります。乳幼児や高齢者の下痢では脱水症状を伴いやすく、元気がない、強い倦怠感があるなどの場合は受診が必要です。下痢だけでなく腹痛や血便がある場合は重症の感染性腸炎(食中毒)、潰瘍性大腸炎、がんなどにも注意が必要です。
- 月経前緊張症・月経前不快気分症
-
月経前・月経中の頭痛やむくみ、気分のおちこみ、いらいら、情緒不安定などは多くの女性が経験する症状ですが、なかには症状が強く、生活に支障をきたしてしまうこともあります。婦人科でのホルモン剤治療が有効な場合がありますが、もともとのパニック障害や神経症の症状が強く現れている可能性も否定できません。女性外来ではどのような治療の選択肢があるかを患者さんと一緒に考えていきます。
- 原発性アルドステロン症
-
副腎からアルドステロンが自律的に過剰分泌される病気です。高血圧症の患者さんの5%程度が原発性アルドステロン症と推定されています。副腎腫瘍や過形成からのアルドステロン過剰分泌が原因となります。副腎腫瘍が原因の場合は手術治療が選択されますが、過形成の場合は手術治療の対象とならず、アルドステロン拮抗薬(ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬)による治療を行います。
- 後頚部の痛み
-
首の後ろの慢性的な疼痛は頚部から背中にかけての筋肉(主に僧帽筋)の過緊張、すなわち肩こりによることが多いです。後頚部から頭皮へのビリビリした痛みは大後頭神経痛とよばれ凝った筋肉による絞扼性障害のひとつです。一方、急激に起こる、非常に激しい後頚部痛は脳に分布する動脈の血管壁解離が原因のことがありますので、すみやかに救急外来へ受診してください。
- 更年期の体調不良(婦人科)
-
日本人の平均閉経年齢は約50歳ですが、閉経前の5年間と閉経後の5年間とを併せた10年間を「更年期」といいます。更年期に現れるさまざまな症状の中で他の病気に伴わないものを「更年期症状」といい、その中でも症状が重く日常生活に支障を来す状態を「更年期障害」と言います。更年期障害の主な原因は女性ホルモン(エストロゲン)が大きくゆらぎながら低下していくことですが、その上に加齢などの身体的因子、成育歴や性格などの心理的因子、職場や家庭における人間関係などの社会的因子が複合的に関与することで発症すると考えられています。更年期障害の症状は大きく3種類に分けられます。(1)血管の拡張と放熱に関係する症状:ほてり、のぼせ、ホットフラッシュ、発汗など。(2)その他のさまざまな身体症状:めまい、動悸、胸が締め付けられるような感じ、頭痛、肩こり、腰や背中の痛み、関節の痛み、冷え、しびれ、疲れやすさなど。(3)精神症状:気分の落ち込み、意欲の低下、イライラ、情緒不安定、不眠など。更年期障害の特徴の一つは症状が多彩なことですが、これらが他の病気による症状ではないことを確認する必要があります。
- 股関節周囲の痛み
-
片方の脚に体重をかけると痛い、脚の付け根内側に痛みがあるなどの場合は股関節の問題があるかもしれません。大腿部や臀部の外側の痛みは股関節だけでなく股関節を囲む筋肉や靭帯・腱の問題が起こっている可能性もあります。脚の付け根に硬結を触れる場合は鼠径ヘルニアかもしれません。ランニングやサッカーなどのキック動作で恥骨に炎症が起きた場合もそけい部や恥骨の前面に痛みが生じます。
- 黒色便・タール便
-
真っ黒なドロドロした黒色便をタール便(コールタールの色ににているから)と呼び、胃や十二指腸・食道などの肛門から離れた部分の消化器器官で出血が起こっている可能性があり胃カメラや大腸の検査が必要です。貧血の治療に鉄剤を内服していても便の色が黒くなります。
- こむらがえり
-
睡眠中にふくらはぎや足の筋肉に痛みを伴うけいれんがみられることがあります。健康なひとにもおこりますが、脱水や血液中の電解質異常、糖尿病などにともなう末梢神経疾患、甲状腺機能低下症などが原因になることがあります。利尿剤やアルコール依存が原因の場合もあります。
- 転びやすい
-
病後や高齢になったための足腰の弱りなど転びやすくなったなと感じることがあります。頚椎ヘルニアで頸髄が圧迫された場合や小さな脳梗塞が多発している、末梢神経の病気で足の裏の感覚が鈍くなっている場合など病気が原因のこともあります。また、特に高齢者では睡眠導入剤の内服により夜間に目が覚めた時や起き抜けにふらついて転ぶこともあり薬の内服にも注意が必要です。
- 口腔がん
-
口腔がんは、口唇がん、舌がん、口底がん、歯肉がん、頬粘膜がん、硬口蓋がんなどに分けられます。これらのうち、舌がんの発生頻度がもっとも高く、口腔がんの約40%を占めます。そのほかには唾液腺から発生するがんなどもみられます。 悪性腫瘍は、(1)病気の進行が速く、できもの(潰瘍、腫瘤)が速く大きくなる、(2)できものの周りが硬い、(3)周囲と癒着していて、境界がはっきりしない、(4)他の部位に転移する、などの性質があります。病期が進むにつれて咀嚼や嚥下、発音が障害されたりします。また、頸部のリンパ節に転移します。さらに進行すると、肺、骨、肝臓など他の臓器に転移し、全身的な症状をおこすようになります。
- 甲状腺がん
-
甲状腺は頸部の下端にあり気管の前面に位置する臓器です。そこから発生する悪性腫瘍が甲状腺がんです。治療は主に手術ですが必要に応じて放射線治療や薬物療法も適応になります。中部ろうさい病院耳鼻咽喉科では他院からの紹介や内科からの依頼など幅広く患者さんを受け入れ、内視鏡下手術も積極的に実施しています。
- 甲状腺機能亢進症
-
自己免疫異常による甲状腺機能亢進症です。自己免疫疾患であり比較的女性に多く体質が影響する部分もあり、しばしば1型糖尿病と同時に見つかります。甲状腺に対する刺激抗体により血中甲状腺ホルモン(fT3, fT4)値が上昇し、動悸、発汗、イライラ感、下痢、体重減少などの症状が出現します。治療としては、まず内服薬が多くで選択されますが、改善が不十分の場合は手術療法や放射性ヨウ素内用療法が行われます。
- 甲状腺機能低下症(橋本病)
-
原発性甲状腺機能低下症で最も多いのは慢性甲状腺炎(橋本病)です。橋本病は自己免疫疾患の一つで、主な症状は甲状腺腫大です。血中甲状腺ホルモン(fT3, fT4値)の低下と甲状腺刺激ホルモン(TSH)値の上昇、甲状腺に対する自己抗体が陽性となることで診断されます。血中甲状腺ホルモン値が低下するため、徐脈、心肥大、うつ状態、筋力低下、脱毛、皮膚乾燥、過多月経、低体温などの症状がみとめられます。甲状腺ホルモン製剤の内服で補充療法を行います。
対応する診療科
- 高尿酸血症・痛風
-
血清尿酸値7.0 mg/dL以上は高尿酸血症となります。尿酸値が高いだけでは自覚症状はありませんが、長期間の高尿酸血症により関節・足先などに結晶となった尿酸がたまり炎症が生じ、激痛の痛風発作が起こります。 また腎臓結石や尿管結石の原因となり、背部などに激痛を生じます。尿酸の生成抑制薬や尿への排泄促進薬で治療を行います。食事療法としてプリン体の摂取制限が必要となります。
- 更年期障害・更年期うつ
-
閉経前後(40歳から60歳代)の女性は内分泌環境の変化により体調不良を起こしやすくなるようです。ホットフラッシュや発汗異常などの身体的ホルモン欠落症状ばかりでなく、関節痛、頭痛・めまい、倦怠感や意欲低下などさまざまな症状が出現します。内分泌環境の変化ばかりでなく、疲労や精神的ストレスが身体症状の原因になることも少なくありません。更年期障害の治療には婦人科で行うホルモン補充治療が有効な場合がありますが、うつ症状は女性ホルモンの関与以外にもいろいろな増悪因子があり精神・心療内科的治療を必要とすることも少なくありません。女性外来では症状に応じた適切な治療法のアドバイスをいたします。
- 骨粗鬆症
-
骨粗鬆症とは、骨の代謝バランスが崩れ、骨形成よりも骨破壊が上回る状態が続き、骨量が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。日本には約1000万人以上の患者さんがいると推定され、高齢化に伴ってその数は増加傾向にあります。骨折としては、脊椎の圧迫骨折、大腿骨頸部骨折、手首や上腕骨骨折などが生じます。一旦骨折が生じますと患者さんの生活の質を著しく悪化させるため予防が重要で内服薬や注射薬などを使用します。
- 骨盤臓器脱
-
骨盤臓器脱とは、骨盤内臓器が通常の位置よりも下垂する状態です。下垂する臓器によって呼び方が異なり、子宮脱、膀胱瘤、直腸瘤などに分類されます。骨盤底の支持機構の破綻が原因となります。出産経験者の約40%が何らかの骨盤臓器脱の症状を呈します。そのリスク因子となるのが経膣分娩や肥満です。症状として下腹部の違和感、尿失禁、便秘などを伴う場合があります。