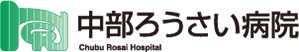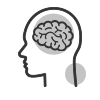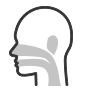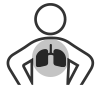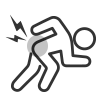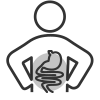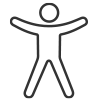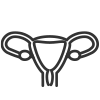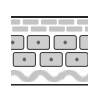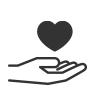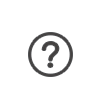症状/疾患・部位 からさがす
- TOP
- 症状/疾患・部位 からさがす
- 「な行」の症状/疾患
「な行」の症状/疾患
- 内頚動脈狭窄症(脳神経外科)
-
脳梗塞の原因の一つです。近年高血圧・高脂血症・糖尿病など生活習慣病の合併や食事形態の変化に伴い患者数は増加傾向です。症状のない内頚動脈狭窄(無症候性)と一過性の脳虚血症状(TIA)や永続する麻痺や構音障害など発症し判明する内頚動脈狭窄(症候性)があります。症状に応じて内科的治療・外科的治療(内膜剥離手術:CEA・頚動脈ステント治療:CAS)が必要か判断します。
対応する診療科
- 内頚動脈狭窄症(脳神経内科)
-
動脈硬化が進行すると頚動脈血管壁に余分なコレステロールが沈着し頚動脈の狭窄がおこります。そのため心臓から脳への血流が低下する、狭窄の原因であるプラークや血栓が一部はがれて多数の脳血管に飛散して詰まり多発塞栓をおこすなど脳梗塞のリスクが高くなります。また、一過性の麻痺や言語障害などの神経症状の出現と回復を来す一過性脳虚血発作(TIA)が起こることもあります。治療は抗血小板薬などの薬物治療に加えて頚動脈ステント留置術や頚動脈内膜剥離術を行う場合があります。頚動脈狭窄は無症候のまま脳ドックで偶然見つかることも多く、その場合も頚動脈超音波検査や頚動脈MRA、脳血流検査などを検討し、脳梗塞のリスク因子の管理や薬物治療など今後の対応を検討します。
- 内分泌疾患(小児)
-
小児内分泌専門医が、低身長や思春期早発症、甲状腺疾患などの疾患について、個々の患者様の日常生活の質を高めることができるように、ご家族と協力して治療を進めて行きます。身長が低い・身長の伸びが悪い、思春期が早いあるいは思春期が遅いなどは病気ではなく体質の場合も多いですが治療が必要な疾患もありますのでご相談ください。
- 乳汁ろう(乳汁漏出症)
-
乳汁漏(にゅうじゅうろう)とは妊娠・産褥期以外の時に乳汁(おっぱい)の分泌が見られる状態です。女性に多い症状ですが男性にも起こります。プロラクチンというホルモンが脳下垂体から異常に分泌されている状態で、脳腫瘍の可能性があります。吐き気どめ・降圧薬などの薬の副作用でも起こるので注意が必要です。血の混じった分泌液が乳頭から出る場合は乳がんの症状のことがあるので早めの受診が必要です。
- 乳がん
-
乳がんは乳腺の組織にできるがんで悪性腫瘍です。乳房のしこり、乳房のえくぼやただれ、左右の乳房の形が非対照になる、乳頭から分泌物が出る、などが症状です。男性にも発生することがあります。乳房の周りのリンパ節や、肺、肝臓、骨、脳などに転移することがあります。乳がんは自分で見つけることのできるがんの1つです。日頃から入浴や着替えのときなどに、自分の乳房を見たり触ったりして、セルフチェックを心がけましょう。セルフチェックで見つけられないこともあるため、定期的に乳がん検診を受けることは非常に重要です。診察(視触診)、マンモグラフィー、超音波検査、針生検検査、CT検査、MRI検査、骨シンチ検査、PET検査等を行います。治療法には、手術、放射線治療、薬物療法があります。
- 尿もれ(尿失禁)
-
尿もれや尿失禁(おもらし)にはお腹に力をいれたとき・咳をした時などに起こる腹圧性尿失禁、急に排尿したくなり間に合わない切迫性尿失禁、自分では排尿したいのになかなか出ず少しずつもれてしまう溢流性尿失禁、排尿機能は正常なのに認知症のためにトイレでの排尿ができない機能性尿失禁などいろいろなタイプがあります。状態や原因に応じてきちんとした治療を受けることが大切です。
- 尿路感染症(腎盂腎炎、膀胱炎、尿道炎)
-
尿路感染症は腎臓、尿管、膀胱、尿道に細菌等が侵入して生じた感染症です。急性膀胱炎は若い女性に多く、症状は排尿時痛、頻尿、尿混濁が3主徴です。急性腎盂腎炎も若い女性に多く、症状は発熱、側腹部痛になります。どちらの病気も抗生剤で治療を行います。また尿道炎は若い男性に多く、症状は排尿時痛、尿道からの排膿になります。尿道炎は性行為を介して感染する場合が多く注意が必要です。
対応する診療科
- 尿路結石
-
尿路結石は発生部位により、腎結石、尿管結石、膀胱結石に分類されます。この中でも尿管結石は強い腹痛(腰痛)、血尿で発症します。夜間救急車で受診するような強い腹痛の原因の多くは尿管結石です。治療法は結石のサイズで異なり、小さい結石(5−10mm未満)は薬を飲んで自然排石を待ちます。また大きい結石(5−10mm以上)は尿道から細い内視鏡を挿入してレーザーで結石を破砕したり、体外結石破砕装置で体外から衝撃波で結石を破砕します。
- 尿路上皮がん(腎盂がん、尿管がん、膀胱がん)
-
腎実質で作られた尿は腎臓内の腎盂(尿の貯まる袋)に移動し、その後尿管を通り膀胱に貯まります。尿意を感じると尿道を介して尿は体外に排出されます。この一連の尿の排泄通路(腎盂、尿管、膀胱、尿道)を尿路上皮と呼び、これらに発生するがんを尿路上皮がん(腎盂がん、尿管がん、膀胱がん、尿道がん)と呼びます。尿路上皮がんの初発症状は何の前触れもなく突然肉眼的血尿(真っ赤な尿)が出ることです。この場合直ちに泌尿器科を受診して下さい。
対応する診療科
- 妊娠糖尿病(産婦人科)
-
妊娠糖尿病とは、妊娠中にはじめて発見された糖代謝異常です。なお、妊娠前から既に糖尿病と診断されている場合等は含まれませんが、より重度の状態ですので、血糖をより厳密に管理する必要があります。妊娠糖尿病は妊娠高血圧症候群、羊水量の異常、肩甲難産、網膜症・腎症を合併する場合があります。胎児も流産、形態異常、巨大児、心臓の肥大、低血糖、多血症、電解質異常、黄疸、胎児死亡などを発症する場合があります。妊婦さんの7〜9%は妊娠糖尿病と診断されるため、きちんと検査を受けましょう。特に肥満、糖尿病の家族歴のある人、高年妊娠、巨大児出産既往のある人などはハイリスクですので必ず検査をうけてください。
- 妊娠糖尿病
-
もともとは糖尿病と言われたことがない方が妊娠に伴って高血糖を来すと妊娠糖尿病と診断されます。特に胎児生育への影響が大きい妊娠初期に厳格な血糖管理を必要とする場合があり、早期からの受診が必要です。妊娠中は継続的に食前食後の自己測定を行い必要に応じインスリン自己注射療法を始めていただきます。出産後多くの方は健常の血糖値に速やかに改善しますが、将来糖尿病になる可能性は高いです。
対応する診療科
- 認知症
-
アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症、前頭側頭葉型認知症を4大認知症といい、認知症の90%以上は4つのどれかに該当するといわれます。なかでもアルツハイマー型認知症が最多で認知症というと物忘れが目立つアルツハイマー型を思い浮かべる人も少なくありません。レビー小体型は幻視や動作緩慢が初期症状です。脳血管性認知症は脳出血や脳梗塞が原因で起こり、もの忘れ・判断力の低下のほか嚥下障害や歩行障害を伴います。前頭側頭葉型では初期には物忘れが目立たず、人格変化が目立ちます。認知症の種類によって進行の速度や形式が変わるため早期診断が重要です。また認知症の中には外科手術による治療や内科疾患に伴う進行抑制可能な認知症、薬物による偽性認知症などがありMRIや脳血流検査、血液検査などで鑑別していきます。
- 眠気
-
眠気のほとんどは生理的なものですが、十分な睡眠時間があるのに昼間も眠い場合は睡眠時に無呼吸状態をくりかえす睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。女性は月経前症候群の症状のひとつとして眠気が認められます。高齢者が昼間寝てばかりいるのは加齢で眠りが浅くなったせいもありますが、認知症症状(アパシー・無気力)や慢性硬膜下血腫などの傾眠傾向の場合もあるので注意が必要です。また眠気とは異なるものの、突然ごくわずかの時間意識が途切れる場合はてんかんの発作のこともあります。
関連疾患・鑑別疾患
対応する診療科
- ネフローゼ症候群
-
ネフローゼ症候群は尿からタンパク質がもれて、血液中のタンパク質であるアルブミンが少なくなることで体全体がむくむ病態です。ひとつの病気ではなく、同じような症状を出す様々な病気の総称です。足や顔のむくみや尿の泡立ちがよくある症状ですが、ひどくなると肺や腹部、心臓や陰のうにも水がたまります。血液中のコレステロールが増えたり、腎不全、血栓症(血管が詰まる病気)、感染症を合併する危険性もあります。腎生検(入院して腎臓に針を刺し、採った腎臓を顕微鏡でみる検査)で原因となる病気を調べて、結果に応じてステロイドや免疫抑制といった薬を中心とした治療を行います。
- 喉がつまる
-
食事は問題なく食べることができるのに、喉に何か詰まっているような感じがして気になって仕方がないことがあります。通過障害のない喉の閉塞感はアレルギー性鼻炎の後鼻漏、逆流性食道炎などの症状のこともありますが、ストレスが原因で喉が感じやすくなったための心身症のこともあります。まずは耳鼻科や内科(消化器科)で通過障害の原因がないことを確認しましょう。
- のぼせ
-
のぼせとは頭・顔などが異常にな熱さを感じることです。「ほてり」とともに更年期の女性ホルモン分泌の低下による身体症状としてよく知られています。緊張したときや感情がたかぶったときに出現しやすく、睡眠中にも起こり「寝汗」になる場合があります。のぼせは更年期症状としてだけでなく、自律神経失調症状として年齢に関係なくおこることがあります。甲状腺疾患や高血圧など他の疾患との鑑別が必要です。
- 脳炎・髄膜炎
-
脳炎・髄膜炎とは脳や脊髄、これらを包む髄膜に炎症が起こった状態です。原因としてウイルスや細菌などの感染性、自己免疫システムの異常から炎症を起こす自己免疫性、薬剤性や腫瘍性などがあります。発熱・頭痛・悪心嘔吐・後頚部痛・けいれん発作が起こり、意識障害や異常行動など多彩な症状が起こります。出来るだけはやく受診しMRIなどの画像検査、腰椎穿刺による髄液検査などを行い総合的に診断しますが、早期診断と治療が重要です。
- 膿胸
-
膿胸とは、胸の中(胸腔)に膿(うみ)や、膿様の液体が貯留した状態のことをいいます。原因としては、肺炎などで肺の中に生じた炎症が胸腔におよぶことによって生じるものや、食道や肺などに対する手術後の合併症として発症するものなどがあります。症状としては、発熱や胸の痛み、息苦しさがあります。また、重症化するとショック症状(血圧低下、意識障害)を起こすこともあります。治療は、適切な抗菌薬の投与と膿をからだの外に出すこと(排膿)ですが、これらの治療を行っても良くならない場合は手術を行います。
- 脳梗塞(脳神経内科)
-
脳梗塞とは何らかの原因で脳の動脈が閉塞し、血流が途絶して脳の一部が壊死してしまう病気です。脳血管の動脈硬化が原因の脳血栓と、心臓でできた血栓や頚動脈壁のコレステロールのかたまりや血栓が脳内の血管に達して詰まる脳塞栓とがあります。脳の障害部位によって、半身麻痺やことばの障害、感覚障害などいろいろな症状が出現し、しばしば後遺症が残ります。発症から数時間以内であれば血栓溶解療法(t-PA静注療法)や血管内カテーテル治療で壊死に陥りかけた神経細胞を救済できる可能性があります。高血圧や糖尿病、心房細動、脂質異常症、慢性腎臓病、喫煙、肥満などが発症の危険因子です。
- 脳出血
-
一般的に高血圧に関連した脳出血(高血圧性脳出血)が最も多く、高齢化に伴い発症するタイプの脳出血(脳皮質下出血)や内服している血液サラサラ薬(抗凝固薬・抗血小板薬)により二次的に生じる脳出血も増大傾向です。外科的手術が必要な場合、全身麻酔下に開頭血種除去あるいは内視鏡下血種除去、脳室ドレナージなどを行います。
- 脳腫瘍(良性・悪性)
-
脳腫瘍は脳実質自体から生じる脳腫瘍(グリオーマとも呼ばれる)と、脳・神経の周囲の構造物(硬膜や神経鞘)から生じる腫瘍(良性腫瘍が多い)に大きく分かれます。また、がんの中には脳に腫瘍が転移するものがあります。麻痺や言語障害、視野障害など症状は部位により様々です。まずは画像診断をすることをお勧めします。必要に応じて手術や薬物治療、放射線治療など組み合わせて治療します。確定診断には手術による病理検査が必要です。
対応する診療科
- 脳脊髄液減少症(低髄液圧症候群)
-
交通事故・スポーツ外傷などが原因で脳脊髄を覆う膜(硬膜)が破れ、脳脊髄が髄液腔外へ漏れて減少するため頭痛・頚部痛・めまい・耳鳴り・倦怠感・不眠・もの忘れなどさまざまな症状が起こります。仰臥位など寝ている姿勢ではなんともないのに立ち上がると(立位)症状が出現することが特徴です。心因性の不定愁訴と区別がつきにくく、MRIやシンチグラフィーなどで髄液の漏れを証明しなければなりません。髄液が漏れている場所が確認できれば硬膜下血液パッチ(ブラッドパッチ)などの手術治療が可能です。
- 脳動静脈奇形
-
脳卒中を起こす稀な疾患です。頭部MRIおよび造影検査にて診断されます。動静脈奇形・硬膜動静脈瘻では外科治療として開頭手術、血管内治療があり、症例により放射線治療を組み合わせます。
対応する診療科