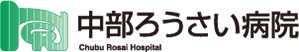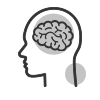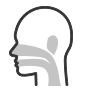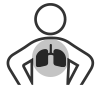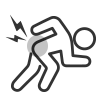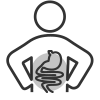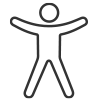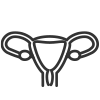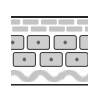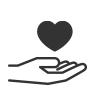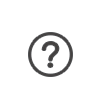症状/疾患・部位 からさがす
- TOP
- 症状/疾患・部位 からさがす
- 「ま行」の症状/疾患
「ま行」の症状/疾患
- まぶたのけいれん
-
眼瞼(まぶた)けいれんとは眼の周りの筋肉がけいれんして目が開けにくくなる、まばたきが上手にできないなどの症状です。顔半分が自分の意思と関係なくピクピクするのは顔面痙攣で、口のひきつるような動きが特徴です。人前で緊張したり、ストレス、疲労などが引き金になります。両者とも抗けいれん薬や神経ブロック(ボトックス治療)で治療しますが難治性の場合は超音波や放射線治療、脳外科手術が有効な場合もあります。眼瞼周囲のけいれんは顔面神経麻痺の治癒過程でおこることもあります。
- 慢性炎症性脱髄性多発神経根炎(CIDP)
-
CIDPとは四肢の筋力低下やしびれ感・知覚鈍麻が2ヶ月以上にわたりゆっくり進行する末梢神経の炎症性疾患です。早期発見・早期治療が非常に重要です。治療にはステロイドホルモン剤の大量投与、血液製剤である免疫グロブリンの大量療法、血漿交換などを行います。血管炎に伴う神経障害や糖尿病性神経障害などとの鑑別が必要であり、神経伝導検査や髄液検査を行い診断します。(厚労省指定難病)
- 慢性腎臓病
-
慢性腎臓病とは、尿の異常(多くは蛋白尿)や腎機能低下(eGFR 60ml/min/1.73m?未満)が3か月以上つづく状態を指します。国民病と呼ばれるほど数が多く、成人の8人に1人、80歳台の2人に1人が慢性腎臓病です。蛋白尿が多くeGFRが低い人ほど末期腎不全(透析か移植が必要になること)になりやすく、心筋梗塞や脳梗塞といった病気にもなりやすいと言われています。慢性腎臓病では低下した腎機能が回復することは基本的に期待できず、進行予防のためには糖尿病、高血圧、高尿酸血症など生活習慣病の治療や食事管理、適度な運動、禁煙といった生活習慣の是正が大切です。
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
-
準備中
- 味覚障害
-
味覚障害(味を感じない)はコロナウイルスを含めた感冒症状をおこすウイルス感染後によく起こります。ほとんどは自然に改善します。亜鉛・鉄・ビタミン不足でおこることもあります。味を感じない症状の他に、本来の味と異なる感じがする、何をたべても不味く感じる・何も食べていなくても口の中に苦味や塩味を感じるなどの味覚異常がおこることもあります。
- 耳鳴り
-
耳鳴り(耳鳴(じめい))は周囲の音ではなく、耳の中で発生している雑音です。難聴を伴うことがよくあります。静かな場所や眠ろうとしている時に特に気になります。動脈硬化のため生じた頸動脈血流の乱れを耳鳴りとして感じることがあります。
- 未破裂脳動脈瘤
-
脳ドック等で発見されるものが多く、通常は無症状です。部位、大きさ、経過観察中の形状変化の有無等にて治療方針を決定します。破裂動脈瘤(くも膜下出血の原因)と同様、開頭手術と血管内治療があります。画像による経過観察(保存的治療)が選択されることもありますので専門医のいる機関を受診することがやはり重要と思われます。
対応する診療科
- むくみ
-
足の腫れ・むくみはよくある症状ですがその原因はさまざまです。全身性の原因として心不全や腎不全、低栄養などがあり息切れや動悸を伴う場合は早めに受診しましょう。局所的な原因としては静脈瘤・静脈血栓、リンパ浮腫などがあります。高齢者や座っている時間が多い方にはむくみがよく認められます。肥満や水分の取りすぎもむくみの原因になります。女性は月経前にむくみがでることもあります。病的ではないむくみの解消には歩くなどの運動、圧迫ストッキングの着用などが有用です。
- むせる
-
たべものや水が本来の通り道である食道ではなく、肺につながる気道に入ってしまった時に、異物をだそうとして反射的に起こるのがむせです。脳梗塞などが両側大脳半球におこると仮性球麻痺となり誤嚥や嚥下障害がおこります。いつも喉に痰が絡んでいる、ご飯粒が鼻から出てくる、勢いよく水を飲むとむせるなどの症状が頻回におこる時は嚥下力の衰えを意味します。また筋萎縮性側索硬化症(ALS)など筋力低下を起こす疾患で舌の筋力低下・筋萎縮がおこると通過障害はないのに上手く飲み込むことができなくなります。
- 目の出血(結膜出血)
-
眼球の白い部分の出血は結膜下の小血管が出血したもので、軽度の違和感はありますが痛みや痒みはありません。ドライアイや高血圧・睡眠不足など様々な原因で起こります。1、2週間で自然治癒することが多いですが長く続く場合や、何度もくりかえす場合は受診しましょう。
- 目の充血
-
目が赤くなる原因は、外部からの刺激や炎症、目の酷使による疲労などが考えられます。充血がなかなかとれない場合はアレルギー、感染性結膜炎、ドライアイ、ぶどう膜炎といった疾患による炎症が充血の原因かもしれません。
- めまい(脳神経内科)
-
めまい(めまい感)は天井や周囲がくるくる回る回転性めまいとふわふわする動揺性めまいに大別されます。脳血管障害に伴うめまいは回転性で悪心・嘔吐・ふらつきを伴うことが多いです。頭位変換性めまいは内耳性めまいともいわれ、耳石が三半規管内で動揺するために起こります。
- めまい(耳鼻科)
-
耳鼻咽喉科であつかうめまいは、良性発作性頭位めまい症状(BPPV)、メニエール病、突発難聴、前庭神経炎などです。眼の動き(眼振)、歩き方、きこえの変化、などを診察しています。脳の疾患が疑われた場合、脳神経内科にご相談しています。治療としては、お薬の処方、リハビリテーション(寝返りをうつリハビリ、指先を目で追うリハビリ、など)のご紹介、生活のアドバイスなどを行っています。
- もの忘れ
-
誰でも年齢が重なると「もの忘れ」をします。しばらく経ってから思い出すことのできる場合は年齢相応のもの忘れと考えられます。それに対して「昨日孫が来て一緒に遊んだ」など出来事自体を忘れてしまうもの忘れが頻回に起こる場合は認知機能の低下によるもの忘れの可能性があります。
- もやもや病
-
脳卒中と似た病態を起こす稀な疾患です。一時的な言語障害や失語、手足の麻痺がしばしば認められます。拡張した「もやもや血管」が頭部のMRIや血管造影で認められます。脳血流を維持できるように血管のバイパス手術を行います。