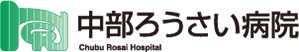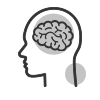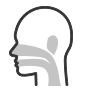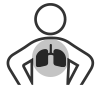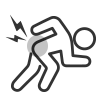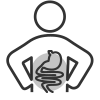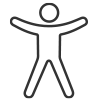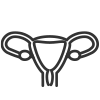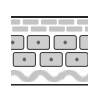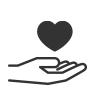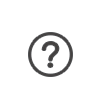症状/疾患・部位 からさがす
- TOP
- 症状/疾患・部位 からさがす
- 「あ行」の症状/疾患
「あ行」の症状/疾患
- あしがつる
-
睡眠中にふくらはぎや足の筋肉に痛みを伴うけいれんがみられることがあります。健康なひとにもおこりますが、脱水や血液中の電解質異常、糖尿病などにともなう末梢神経疾患、甲状腺機能低下症などが原因になることがあります。利尿剤やアルコール依存が原因の場合もあります。
- 足の痛み
-
足の親指の付け根が赤く腫れ、激痛を伴う時は「痛風」の可能性があります。足の甲や足、膝関節、手・肩関節にも起こる場合があります。足のかかとが痛くなる場合は足底筋膜炎かもしれません。ハイヒールの常用、扁平足や長時間の立位、ランニングなどの足底への負担で起こります。整形外科的な異常のほかに動脈硬化によって脚の動脈が狭くなる・詰まるなど閉塞性動脈硬化症で足の痛みが起こります。
- IgA腎症
-
IgA腎症は、慢性糸球体腎炎の中で最も頻度の高い病気で、小児や若い人にも起きます。血尿と蛋白尿が続き検診で発見されることが多いです。扁桃腺に代表されるリンパ組織で、異常をもったIgAという免疫タンパク質が過剰に作られ、それが腎臓を障害すると言われています。尿の赤み(血尿)を自覚する人もいますが、多くは無症状です。しかし長い年月をかけて腎機能が低下しやすく、成人では20年で30〜40%が末期腎不全(透析か移植が必要になること)になります。特に蛋白尿が多いとか、病理検査の結果が重いと、腎不全になりやすいと言われています。寛解(蛋白尿と血尿を消失させること)させ、将来腎不全にならないように治療を行います。
- 悪性胸膜中皮腫
-
悪性胸膜中皮腫は、肺の表面をおおう胸膜と呼ばれる部位から発生する悪性腫瘍で、多くはアスベスト(石綿)が原因と言われています。初期の段階では症状がないことが多いのですが、腫瘍が大きくなると、胸の痛みや咳、胸水貯留による息苦しさを認めるようになってきます。非常に治りにくい疾患のため、手術や化学療法、放射線治療を組み合わせた集学的治療を行います。過去にアスベスト(石綿)を取り扱っており、現在、胸の痛みや咳などの症状がある方、その他ご心配がある方はご相談ください。
- アルコールによる健康被害
-
過度な飲酒が続くと、肝障害(肝炎・肝硬変)、糖尿病、心疾患、高血圧、胃腸障害などが起こりやすくなります。末梢神経障害により手足のしびれや筋肉の痩せがおこるばかりでなく認知症やけいれんの症状が現れることもあります。
- アルツハイマー型認知症
-
認知症の中で最も多く脳の一部が変性することによりもの忘れなどが生じる病気です。原因はまだ完全には解明されていないものの脳の神経細胞に特定のタンパク質がたまることが関与していると考えられています。遺伝性のものもあります。現段階では根治治療はありませんが進行抑制のための薬物療法を行います。
- アレルギー性鼻炎(小児)
-
小児科ではこどものアレルギー疾患に対応しています。花粉症に関してはスギ花粉症とダニ花粉症に対して舌下免疫療法を行います。 花粉症に対しては花粉飛散時期の1か月くらい前からアレルギーを抑える薬を内服することをお勧めします。
- アレルギー性鼻炎
-
くしゃみ、鼻みず、鼻づまりが主な症状です。スギ、ヒノキなどの花粉やダニ、ハウスダストやペットなどが原因となります。 中部ろうさい病院耳鼻咽喉科では内服治療で効果が乏しい人に対してCO2レーザーによる粘膜焼灼や全身麻酔下で選択的後鼻神経切断術を行います。
- 息切れ・息苦しさ
-
息がしにくくなる不快な感覚のことです。胸が締め付けられる、空気が足りないような感じ(吸えない・吐けない)などと表現されます。喘息や肺炎などの呼吸器疾患の他に心不全でも息切れ・息苦しさが現れることがあります。重度の貧血の場合も酸素必要量が増えるため動作時に息切れがします。
- 育児の悩み
-
育児の悩みは母親がひとりで抱えてしまうと解決が難しくなってしまいます。中部ろうさい病院では産婦人科・小児科で成長発達についての相談を受けています。また女性診療科(女性総合外来)では、育児そのものの悩みばかりでなく、育児と仕事の両立など働く女性としての悩みについてもお話しをおききします。
- インプラント(人工歯根)
-
抜歯したり、あるいは自然に脱落したりして歯がなくなると、従来はブリッジや入れ歯を入れることにより機能を補ってきました。しかし最近では、デンタルインプラント治療も一般的になっています。デンタルインプラントを入れるためには埋入手術が必要となります。 デンタルインプラントの植立後は、良好な状態を維持するために厳格な口腔清掃が必要です。これが長期間の予後(よご)を左右する重要な鍵となります。さもなければデンタルインプラントがぐらつき始め、除去しなければならなくなります。したがって、手術を受ける患者にもそれなりの心がけが必要となります。
対応する診療科
- 胃がん(消化器内科)
-
消化管(食道、胃、大腸)がんでは、内視鏡検査やCT、エコーなどを行い、がんの大きさや深さ(深達度)、転移の有無を調べ、進行度(ステージ)に応じて内視鏡的治療(内視鏡的粘膜切除術(EMR)、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD))、化学療法(抗がん剤、分子標的薬、免疫チェックポイント阻害剤など)、放射線療法、手術療法といった治療を、外科や放射線科と密接に連携し、もっとも適切な組み合わせを選択・併用し、治療を行っています。
- 依存症
-
アルコール(飲酒)、ニコチン(たばこ)、薬物などの物質依存症と、ギャンブル、買い物などの行動や習慣に関する依存症が知られています。これらは特定の物質や行動を続けることで脳に変化がおきて症状が引き起こされる病気で本人のこころの弱さのために起きている現象ではありません。依存症について本人や周囲が正しい知識を持ち、適切な支援や治療を受けることが大切です。
- ウィルス性肝炎
-
急性肝炎やB型肝炎ウィルス、C型肝炎ウィルスによる慢性肝炎などの診断と治療を行っています。B型肝炎はインターフェロンと核酸アナログ製剤(エンテカビル、テノホビルなど)で治療を行っており、ほとんどの患者さんで肝臓の炎症を抑え、良好なウィルス制御ができるようになっています。C型肝炎の治療の進歩は目覚ましく、直接作用型抗ウィルス薬(DAA;Direct Acting Antivirals)の治療で、95%以上のウィルス排除が可能となりました。
- うつ病
-
気分の落ち込み、意欲の低下、不眠が持続する疾患です。今日では早期の治療により寛解が望めます。
- 嚥下障害
-
たべものや水が本来の通り道である食道ではなく、肺につながる気道に入ってしまった時に、異物をだそうとして反射的に起こるのがむせです。脳梗塞などが両側大脳半球におこると仮性球麻痺となり誤嚥や嚥下障害がおこります。いつも喉に痰が絡んでいる、ご飯粒が鼻から出てくる、勢いよく水を飲むとむせるなどの症状が頻回におこる時は嚥下力の衰えを意味します。また筋萎縮性側索硬化症(ALS)など筋力低下を起こす疾患で舌の筋力低下・筋萎縮がおこると通過障害はないのに上手く飲み込むことができなくなります。
- 炎症性腸疾患
-
年々増加傾向にあるクローン病、潰瘍性大腸炎といった炎症性腸疾患は、ヒトの免疫機構が異常をきたし、自分の免疫細胞が腸の細胞を攻撃してしまうことで腸に炎症を起こす病気で、慢性的な下痢や血便、腹痛などの症状を伴います。重症度や患者さんの社会的背景を考慮し、薬物療法を中心に治療を行い、難治例に対しては生物学的製剤(TNFα阻害薬、IL-12/23阻害薬など)を選択し、最適な治療を行います。
- おりもの
-
おりものとは子宮頸部、子宮内膜、膣、汗腺からの分泌物です。おりものには膣内を清潔にする働きがあります。性状には個人差があり、月経周期によって量や粘性・色調が変わります。月経後しばらく経っているのにおりものが茶褐色、豆腐カス状、黄・黄緑色の場合や、発熱や腹痛・腰痛を伴っておりものが増えた時などは病的なおりものの可能性があります
- おやしらず(智歯周囲炎)
-
智歯(親知らず)の萌出に際してみられる周囲炎症を特に智歯周囲炎(ちししゅういえん)と呼び、20歳前後の若い人に発生する頻度の高い疾患です。最も遅く、また最も後方に萌出する智歯は、萌出異常をきたし、完全萌出せず歯肉が歯冠を部分的に覆ったままになりやすいため、不潔で、歯肉の炎症をおこしやすくなっています。 智歯周囲炎が周囲の軟組織や顎骨(がっこつ:あごの骨)に波及して顔が腫れたり、口が開きにくくなったりすることがあります。 抗菌薬や消炎鎮痛薬を投与し消炎させた後、萌出位置の異常があったり、炎症をくり返しているような場合は、智歯を抜歯します。
対応する診療科