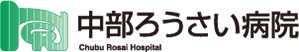リハビリテーション科の診療内容
- TOP
- 診療科・担当医のご案内
- リハビリテーション科
- リハビリテーション科の診療内容
概要
リハビリテーション
急性期リハビリテーション
脳卒中、骨折、心疾患、感染症、各科手術後に対し、病状や病態に合わせた運動療法を中心としたリハビリテーションを開始し、身体機能の維持や回復、日常生活動作の再獲得にむけた訓練、合併症の予防を行います。高齢化社会おいては、短期的な入院でも認知機能、筋力や体力、生活能力の低下が発生することが知られており、これらの弊害を最小限にとどめられるよう、各診療科や病棟とも連携し、早期からのリハビリテーションの介入を進めています。
脊髄損傷
脊髄疾患・脊髄損傷では、上下肢麻痺、膀胱直腸障害、呼吸障害、起立性低血圧、疼痛、褥瘡など様々な症状や合併症を生じることがあります。当院では、急性期から慢性期のそれぞれの時期に起こる問題に関して、入院や外来診療で対応しています。長期的なリハビリテーション入院の受け入れは難しいですが、評価や検査、リハビリテーション目的の短期入院や外来訓練については受け入れの相談を随時行っています。
特に脊髄損傷後に問題となる排泄障害に関しては、体調維持に非常に重要であり、適切に対応していくことは社会参加の手助けになると考えられています。排尿障害に関しては、尿流動体検査やその治療を泌尿器科(例えば、ボトックス膀胱注入療法など)と連携して行っています。排便障害に対しては、従来の薬物治療に加え、経肛門的洗腸療法の導入や指導も行っています。
痙縮
脳卒中や脊髄損傷後の手足のつっぱり(痙縮)により、日常生活に支障が出ている患者さんに対して、抗痙縮薬調整、ボツリヌス毒素注射、装具療法、ストレッチなどの運動療法、物理療法として拡散型衝撃波や低周波電気刺激などを行っています。ボツリヌス毒素治療では、安全・的確に実施できるよう超音波や電気刺激装置を使用しています。
また、重度の痙縮に対してバクロフェン髄髄腔内投与(ITB)療法のトライアルや、当院でITB療法を行った患者さんの薬液補充も行っています。
切断
上下肢の切断術後の装具や自助具、義手義足の検討・作成を行い、日常生活動作訓練を進めています。特に当院では上肢切断や上肢欠損に対する能動義手や筋電義手の導入は、症例や経験が非常に豊富です。筋電義手は電動モーターを力源とした体外力源式義手で、体の筋肉の一部の筋電信号を使ってモーターをコントロールして指の開閉などを制御していきます。能動義手や筋電義手を使いこなすには、適切な訓練が必要であり、患者さんやご家族、作業療法士や義肢装具士と相談しながら、個人や目的にあった訓練や義手を検討していきます。
摂食嚥下障害・訓練
嚥下障害が疑われる患者さんや、現在の食事の食物形態を変更したり、安全性の確認をしたい患者さんに対する嚥下機能評価(嚥下造影検査、嚥下内視鏡検査)を実施しています。その結果に基づいて、誤嚥を予防するための安全な食物形態や食事姿勢の指導を行い、必要に応じて摂食嚥下リハビリテーションを実施しています。入院中の患者さんだけでなく、外来での検査も行えますので、ご相談ください。
心臓リハビリテーション
心臓リハビリテーションは、心臓病の方が心機能や体力を安全に回復し、再発を予防するためのプログラムです。リハビリテーション部では、循環器内科の指導の下、心肺負荷検査に基づいた運動療法を中心としたリハビリテーションプログラムを実施しています。
両立支援
病気や障害を抱えながらも働く意欲・能力のある労働者が、適切な治療を受けながら,就労を継続できるようにすることが治療と仕事の両立支援です。ケガや病気などでリハビリテーション科が関わり両立支援を希望する患者さんに対して、入院中できるだけ早期から支援を開始しています。入院や外来でのリハビリテーションの中で、日常生活自立にむけた訓練に加え、仕事に必要な動作や作業の訓練も取り入れ、身体機能の維持や回復を促すことで復職や就労継続を目指します。また、当院には治療就労両立支援センターが併設されており、両立支援コーディネーターや院内の多職種と連携して治療と仕事の両立に向けた調整が行えるよう支援しています。